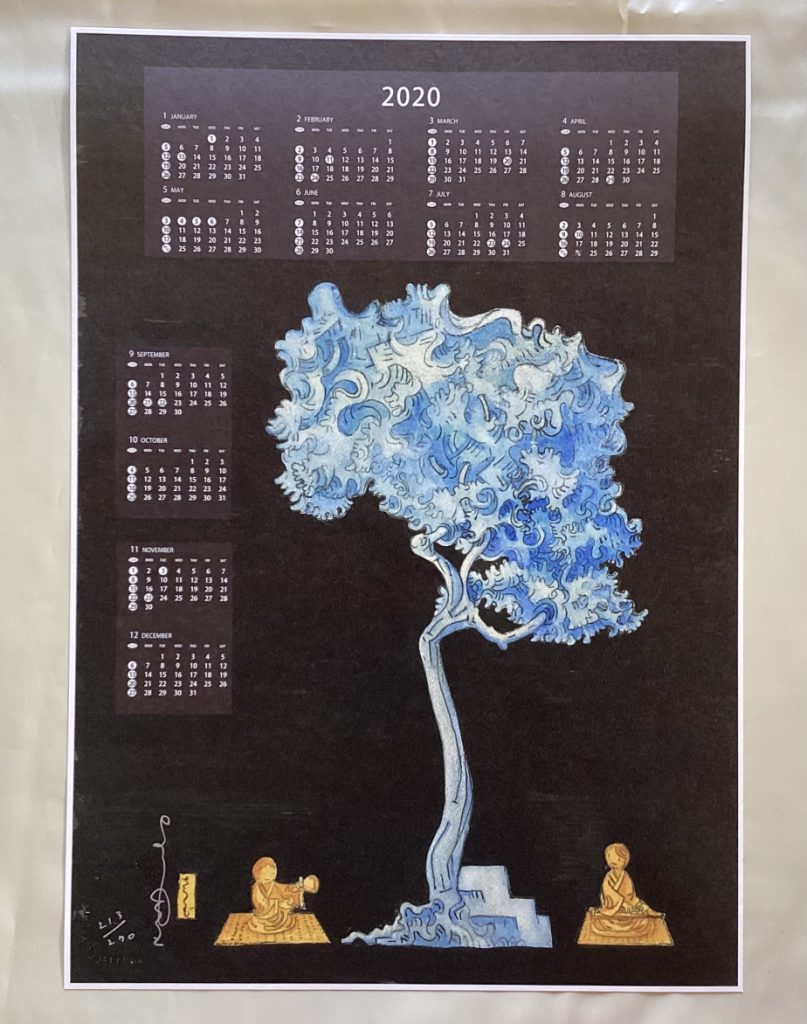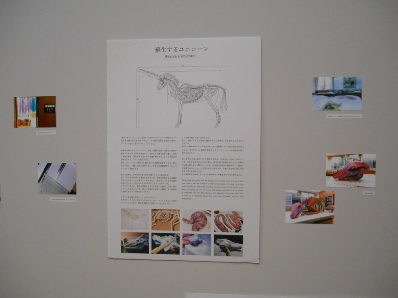三重県立美術館(以下「三重県美」)で開催中の「シャルル=フランソワ・ドービニー展 印象派へのかけ橋」鑑賞の名古屋市美術館協力会ミニツアーに参加する前に、三重県美・地下1階の講堂で鈴村学芸員のスライド・トークを聴きました。下記は、その要約です。
◆スライド・トーク・「1870-71 ロンドン」 本日のスライド・トークのタイトルは「1870-71 ロンドン」です。1870年から1871年にかけて起きた事柄に絞ってお話します。シャルル=フランソワ・ドービニー(1817-187)は、フランスの第二帝政期(1852-70)に活躍した風景画家です。ポール・ドラローシュのアトリエで学び、1850年代に風景画家としての評価が高まりました。1870年にはロンドンに滞在し、モネとピサロを画商のポール・デュラン=リュエルに紹介しています。
本日のスライド・トークの主題は「ドービニーがどのようにしてモネとピサロをデュラン=リュエルに紹介したか」です。
1 時代背景
1870/7/19 フランスがプロイセンに宣戦布告
9月 ナポレオン三世がプロイセンの捕虜となり帝政廃止。共和国(臨時国防政府)樹立宣言
9/20~ プロイセンによるパリ包囲開始。深刻な食糧不足
1871/1/28 パリ降伏
2/26 仮条約。50億フランの賠償金、アルザス=ロレーヌの割譲
3/1 国民衛兵中央委員会が結成される
3/18 大砲事件(武装解除に対する市民の抵抗、蜂起) → ヴェルサイユへ政府が移る
3/28 パリ・コミューン宣言
5/21 ヴェルサイユ軍のパリ侵攻、市街戦の開始「血の一週間」 → 政府軍の勝利(5/28)
2 画家たちと1870-71
1870/7/19 フランスがプロイセンに宣戦布告
9/2 ナポレオン三世がプロイセンの捕虜となる → 9/4 第二帝政廃止
9/8 ポール・デュラン=リュエルがロンドンに向け出発
9/19 エドゥアール・マネ、ジェームズ・ティソはパリに残る
9月終り クロード・モネ ロンドンへ 家族と合流
10月 シャルル=フランソワ・ドービニー ロンドンへ
11月 フレデリック・バジール(1841-1890)がオルレアン近郊で被弾し、戦死
12月 カミーユ・ピサロがロンドンに到着
12/10 デュラン=リュエル、フランス芸術家協会初の展覧会をジャーマン・ギャラリーで開催
12/17 チャリティー・イベントとしてペル・メルで展覧会を開催。ドービニー、モネ出品
1871/1/21 デュラン=リュエルは、ピサロとモネが連絡を取り合えるよう取り計らう 二人はロンドンの美術館で出会う。ターナー、コンスタブルの風景画を鑑賞
5月 モネ、ロンドンを出発、オランダへ。フランスには秋に帰国
5/21 「血の一週間」始まる
5/28 「血の一週間」終結。ギュスターヴ・クールベはスイスに亡命
5月 ドービニーがロンドンを離れる
3 ドービニーの足跡をたどる
1870年10月 ヴィレールヴィル(注:バス・ノルマンディー地方)滞在中にパリ包囲の知らせを受ける。息子のカールは軍隊に、娘セシルと女婿カジミール・ラファン、弟ベルナールと妻、使用人とともにロンドンへ向かう。オテル・ド・レトワールに宿泊。
10/20 ウエスト・ケンジントンに家を借りる
11/2 デュラン=リュエルが画廊をオープン。作品を3点制作
ドービニーは《サリー・サイドから見たセントポール寺院》(1871-73)を描き「信じられないくらいの濃霧」と、ロンドンの濃霧に面食っています。モネも《テムズ川と国会議事堂》(1871)を描いています。現在は、いずれもロンドン・ナショナルギャラリーが所蔵しています。
4 デュラン=リュエルとクロード・モネの出会い
ドービニーは、1870年12月又は1871年1月にモネをデュラン=リュエルに紹介しました。 デュラン=リュエルは、1860年代にバルビゾン派の作品を扱い、1870年代は印象派の作品を扱う画商として画廊での個展を開催し、画家の医療費、絵具代、食費も援助しました。
モネは「デュラン=リュエルのお陰で餓死せずにすんだ」と日記に書いています。 また、ドービニーはデュラン=リュエル経由で、オランダの風景を描いたモネの作品《ザーンダムのザーン川》(1871)を購入しています。
5 モネとドービニー
モネとドービニーは1870年より前から、お互いに知り合っています。モネはブーダンへの手紙に「ドービニーの作品は、私にはとても美しく見えます」と書いています。
ドービニーは印象派の画家たちに極めて好意的でした。1868年のサロンで、モネ、ピサロ、バジールの作品を入選させ、1870年にはモネの入選が叶わず、コローと一緒に審査員を辞任しました。
◎アトリエ船について
ドービニーは1857年にアトリエ小屋を取り付けた「ボタン号」を購入しました。モネも1873年にアトリエ船を入手。ドービニーは、アトリエ船で写生。移動手段でもありました。モネの場合、アトリエ船は移動手段というよりも絵を描く場所で、船を固定し腰を据えて油絵を制作しています。
◆普仏戦争と関係する柳原義達《犬の唄》の原型を紹介
スライド・トークの最後に、鈴村学芸員から「当館の柳原義達記念館では、フランスのシャンソンにちなんだ柳原義達の彫刻《犬の唄》の原型を展示していますので、ご覧ください」と案内があり、歌手のテレザを描いたエドガー・ドガ《カフェ・コンセール(犬の歌)》(1876-77)の画像が示されました。(注:ドガの作品は、歌手の仕草が犬のように見えることから「犬の歌」と呼ばれたそうです。また、碧南市藤井達吉現代美術館で開催された「空間に線を引く」にも《犬の唄》というタイトルの作品が出品され、「《犬の唄》は、普仏戦争で敗れたフランス人の心情を歌ったシャンソンの題名です。抵抗する気持ちを持ちながらも、表面上、プロイセンに対しては犬のように従順さを示す、とフランス人の心情を歌ったシャンソンに託して、作家は第二次世界大戦の敗戦で破壊された人間像を表現しました」と解説がありました。なお、当日、柳原義達記念館に展示されていた石膏の原型は「空間に線を引く」に展示されていた作品の原型ではありませんでした)
Ron.