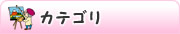◆2019年あいちトリエンナーレ《旅館アポリア》から始まった連作の最後
先日スマホを見ていたら、突然「美術手帖 EXHIBITION」が出現。「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」が豊田市美術館で開催されることを知りました。記事の概要は以下のとおりです。
〈シンガポールを軸にして、アジアを舞台にした作品を展開してきたホー・ツーニェン。(略)本展では、日本をテーマとしたプロジェクトのひとつとして、奇怪かつ滑稽な100の妖怪たちが闇を練り歩く、新作の映像作品《百鬼夜行》を公開する。ホーの日本でのプロジェクトは、あいちトリエンナーレ2019の豊田会場における喜楽亭(きらくてい)の《旅館アポリア》に始まり、2021年春の山口情報芸術センターでの《ヴォイス・オブ・ヴォイド-虚無の声》に続いて、本展が最後となる。(略)第3弾となる本展では、近代から現在まで日本の大衆文化を反映してきた「妖怪」に焦点を当て、戦争の時代を含めて日本の文化史や精神史を浮かび上がらせる(略)〉引用終り。
(URL=https://bijutsutecho.com/exhibitions/8808)
◆「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」は4つの展示室を使った映像作品
早速、豊田市美術館に行くと「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」(以下「本展」)の大きな看板。口を大きく広げた妖怪(山彦)が出迎えてくれました。展覧会場の入口は2階の展示室1。展示室4までの4室を使った展覧会です。順番に映像作品を見ました。入口にはカーテンが引かれ、中は真っ暗。展示室に入ると係員が来て、足元を懐中電灯で照らしてくれます。
◆展示室1 100の妖怪(上映時間16:30)
展示室1は2つのスクリーンに映像を投影。一番大きな壁面には、2台のプロジェクターを使ってパノラマ作品が投影され、左から右へと色鮮やかな妖怪がパレードを続けます。手前の小さな画面には、眠る人々。この作品は手前の画面とパノラマ画面を重ね合わせて見るように制作されていますが、それに気付かず、「手前の画面にも映像があるけど、まあいいや」とパノラマ画面だけに集中してしまいました。今、思い返すと、残念な鑑賞方法でしたね……
妖怪のパレードはエンドレスなので、どこから見てもO.K.とはいえ、本来の始点は土蜘蛛(古代、大和朝廷に服従せず、異民族視された人々)。赤舌、雷獣、鵺、白澤、獏、鳳凰、だいだらぼっち等、延々と行進は続きます。水木しげるの「妖怪図鑑」を見ているようで、理屈抜きに楽しめる作品です。ただ、旧日本兵の姿をした大天狗の登場で「なぜ、日本兵?」と思い始めました。海坊主、船幽霊、産女(うぶめ。赤子を抱いて、腰から下は血まみれ)の後から登場する、河童、キムジナー、魍魎、木霊(「もののけ姫」に出てくる妖精)などは皆、短刀や手榴弾のようなものを身に着けています。旧日本軍の参謀・辻政信にそっくりな坊主や司令官、快傑ハリマオ(昔のテレビドラマの主人公。頭に白いターバンを巻き、黒いサングラス。石ノ森章太郎もマンガを描いた)が出て来て、作者の意図が分かりました。妖怪は太平洋戦争の影を背負っているのです。
◆展示室2 36の妖怪(上映時間16:45)
展示室1「100の妖怪」に登場した妖怪の中から抜粋し、名前・性質などを紹介しています。偽坊主(第二次世界大戦後、多くの日本兵が僧侶に化けた)、二人の「マラヤの虎」(山下奉文・陸軍大将=戦犯として死刑宣告と、日本人盗賊・谷豊=F機関に所属、ハリマオと呼ばれた)なども紹介されました。(注:山下奉文(ともゆき)は、日本軍が英領マレーとシンガポールを攻略した時の司令官。宮本三郎の戦争画《山下、パーシバル両司令官会見図》(1942)に描かれています)
◆展示室3 1人もしくは2人のスパイ(上映時間17:25)
スパイ養成機関「陸軍中野学校」の話、「F機関」(藤原岩市少佐を長とする謀略機関)の話、「マレーの虎」と呼ばれた日本人盗賊・谷豊を諜報員として勧誘する「ハリマオ作戦」、もう一人の「マレーの虎」山下奉文・陸軍大将、マラヤ侵攻時の参謀で敗戦後は僧侶に化けて戦犯の追及を逃れた辻政信の物語などを、「スパイ」という視点から作品化したものです。2019年の《旅館アポリア》と同じように、アニメーションと実写、虚構と史実などを重ねた映像でした。
◆展示室4 1人もしくは2人の虎 (スクリーン1:上映時間8:00、スクリーン2:上映時間8:00)
展示室4は、3つに仕切られています。手前の部屋のスクリーン1では、二人の「マレーの虎」、山下奉文・陸軍大将と日本人盗賊・谷豊の話、辻政信の話および「F機関」の藤原岩市少佐の話を、「虎」という視点で作品化したものを上映しています。
真ん中の部屋のスクリーン2では「虎」のイメージを主題にした作品を上映していました。冒頭、中国や日本で描かれた「虎図」が次々に登場。どの「虎図」もアニメーション。つまり、動いています。次に登場するのが谷豊。1932年から「ハリマオ=虎」としてマライで活動中、1942年に死亡。軍部は、直ちに彼をモデルにプロパガンダ映画「マライの虎」(1943)を制作。第二次大戦中には「千人針」に「千里往って千里還る」という虎のイメージが使われ、戦後の1960年にはテレビドラマ「快傑ハリマオ」(主人公は、盗賊ではなく海軍中佐という設定)として復活。1989年には、陣内孝則が主役の映画「ハリマオ」が制作され、その後も「タイガーマスク」や「ラムちゃん」など、「虎」のイメージは現代まで脈々と続いていることが分かりました。
最後の部屋には、山下奉文・陸軍大将や快傑ハリマオなどに関する資料が展示されています。
◆《旅館アポリア》の再現もあるようです
本展のチラシの裏には、「とよたまちなか芸術祭の特別展示」ホー・ツーニェン《旅館アポリア》Ho Tzu Nyen Hotel Aporia 日時:2021.12.4|土|-2022.1.23|日| 10:00-16:30、休館日:月曜日[2022年1月10日は開館]、年末年始(2021.12.27‐2022.1.4) 観覧料:無料、主催:公益財団法人豊田市文化振興財団、豊田市、会場:喜楽亭(豊田産業文化センター内)と書いてあります。
2019年の《旅館アポリア》は、喜楽亭(高級料理旅館で戦前は養蚕業者、戦後は自動車関係者が利用。その後、現在地に復元移築)の4つの部屋を使った、12分×7本=84分の映像作品(一ノ間「波」、二ノ間「風」、三ノ間「虚無」、四ノ間「子どもたち」)でした。一ノ間「波」は、小津安二郎監督の映画「彼岸花」(1958)が素材で、出演者の顔にスモークがかけられ、一瞬ですが佐分利信や愛知県蒲郡市の三河大島、蒲郡ホテル(現:蒲郡クラシックホテル)が映ります。三ノ間「虚無」も小津安二郎監督の映画「父ありき」(1942)、「秋刀魚の味」(1962)を素材にしています。トリエンナーレの時は「三密」の状態で鑑賞していました。今回の「再現」では新型コロナウィルス感染防止のため、マスク着用、検温、入場制限などの措置が実施されるのでしょうか。
◆最後に
展示室4の最後の部屋を除き映像作品ばかりなので、全てを見ようとすれば、最短でも1時間以上かかります。立ち続けるのは大変ですが、椅子はわずかしかありません。じっくり鑑賞しようと思ったら直接、床に腰を下ろすか、携帯チェアを持参して座って見ると良いでしょう。分かりやすいですが、色々と考えさせられる作品でした。
なお、せっかく豊田市美術館まで来たのですから、本展の鑑賞券で、同時開催のコレクション展「絶対現在 Absolute Present」も鑑賞しましょう。「絶対お得」です。
Ron.