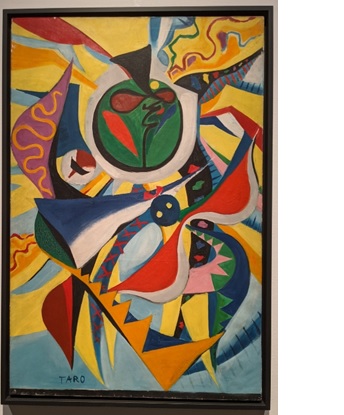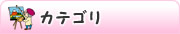美術雑誌によれば、本年に名古屋市美術館へ巡回という「マリー・ローランサンとモード」。最初の巡回先Bunkamura ザ・ミュージアのホームページ(以下「HP」URLは マリー・ローランサンとモード | Bunkamura)を開くと、ガブリエル・シャネル、ポール・ポワレ、マドレーヌ・ヴィオネの名前がありました。図書館で参考になりそうな本を探すと二冊がヒット。それに載っていた内容の一部をご紹介します。
〇 見つけた本
A:『世界服飾史のすべてがわかる本』
能澤慧子 監修 発行所 株式会社ナツメ社 2012年3月12日初版発行
B:『写真でたどる 美しいドレス図鑑』 原題:”How to Read a Dress”
リディア・エドワーズ著 徳井淑子 日本語版監修・訳 小山直子・訳 発行所 株式会社河出書房新社 2021年11月30日初版発行
〇 ポール・ポワレ (Paul Poiret)
1900年に開催された5回目のパリ万国博覧会では(略)川上貞奴の着物姿が話題となり、のちに彼女の名を冠した着物風室内着も販売されました。(略)この流行をいち早く取り入れた代表的なデザイナーがポール・ポワレ。ハイウエストで直線的なシルエットのドレスや、着物のような合わせを持ったドレス、キモノ袖と呼ばれる長い袖をもつドレスを発表しました (A:p.134) 。
Bのp.129に載っていた1912年制作のイブニングコートは、日本の打掛(うちかけ)を思わせるスタイル。ただ、裾幅が狭いので歩幅が制限され、とても歩き難かったろうと思われます。
補足:2022年に豊田市美術館で開催された「交歓するモダン 機能と装飾のポリフォニー」(以下「交歓するモダン」)では《コート》(1920年代) と《デイ・ドレス「ブルトンヌ」》(1921) を展示していました。
〇 マドレーヌ・ヴィオネ (Madeleine Vionnet)
第一次世界大戦後に活躍したデザイナー、マドレーヌ・ヴィオネは立体裁断(注1)の技法を追求し、バイアスカット(注2)やサーキュラーカットなど新しいパターンの衣服を提案。彼女の衣服は、のちのデザイナーたちに強い影響を与えました(A:p.152)。
補足:第二次世界大戦後に発表されたクリスチャン・ディオールのニュー・ルックも、ヴィオネの影響を受けているように思われます。なお、HPは《イヴニング・ドレス》(1938) の画像を掲載。ウエストを絞ったワンピースで、スカートはくるぶしまで。布をたっぷり使った、自然なドレープ(ゆったりと流れるようなひだ)が美しいドレスです。また、「交歓するモダン」では《イヴニング・ドレス》(1922年頃) と《ディ・ドレス》 (1934年頃) を展示していました。
注1 立体裁断 (Draping) :洋裁での制作過程のひとつ。トルソー(人台)に布を当てて、立体的に型紙(パターン)を作ること。マドレーヌ・ヴィオネは、1/2の縮小サイズのトルソーを用いた立体裁断で、バイアスカットを生かしたドレスを作っています。
出展のURL: https://artscape.jp/artword/index.php/立体裁断
注2 バイアスカット (Bias Cut) :1920年代に確立されていった、洋裁での生地の使い方のひとつ。生地の縦と横の地の目に対して斜め方向を利用したカッティングのこと。伸縮性が生まれると同時に動きが出せるので、フィット感があり、きれいなドレープを形作ることができる。
出展のURL: https://artscape.jp/artword/index.php/バイアスカット
〇 ガブリエル・シャネル (Gabrielle Chanel 注:Cocoは愛称)
1918年に、シャネルはジャージー(注3)を用いたドレスを発表する。糸を編み込むことによって伸縮性を持たせた布であるジャージーは、それまで下着の素材としてしか使われていなかったが、シャネルは着飾るだけではなく、生活をするため、生きていくための服をつくった(A:p.138)。
シャネルは、プレタポルテ(注4)を自らのサロンで直接販売するようになった。(略)彼女が作り出す服は、この販売方式に適していた。(略)彼女の服には細々(こまごま)とした飾りはなく、身体を拘束するコルセットも必要なかったが、シンプルな直線と古典的な優雅さがあった。ハイエンドのデザイナーが作る服と、現代生活の要求を結びつける技量は、21世紀のデザイナーたちに受け継がれた哲学である(B:p.138)。
補足:HPに掲載の《ディ・ドレス》 (1927年頃) は、直線的な筒型でローウエスト。胸や腰回りを強調しない、膝丈の少年のようなスタイルです。また、「交歓するモダン」では、カーディガンと対の《イヴニング・ドレス》(1920年代) と黒の《イヴニング・ドレス》(1927年頃) を展示していました。
注3 ジャージー (jersey):ジャージー素材は、イギリスにあるジャージー島で作られたセーターのことを指すが、今ではメリヤス編みなどのニット生地のことをそう呼ぶことも多い。
出展のURL: https://mensfashion.cc/tips/cloth/48499/
注4 プレタポルテ (Prêt-à-porter):フランスでプレタポルテという言葉が生まれたのは1945年のこと。フランスの既製服業者アルベール・ランプールがアメリカの既製服業のシステムを取り入れ、そのとき使われていた「ready to wear」という言葉をフランス語に訳したもの。粗悪なイメージをもっていた既製服だが、60年代に入るとプレタポルテ・メーカーが設立され、品質のよい既製服が提供できるようになった(A:p.159)
補足:デザイナーがデザインした洋服をコレクションとして発表し、顧客の体形に合わせて仕立てて販売するのは、オートクチュール (haute couture)。顧客の好みを仕立てるのではなくデザイナーが提案(A:p.135)
〇 クリスチャン・ディオール (Christian Dior)
1947年は、ファッション史に刻印される年である。ディオールの「ニュー・ルック」が、戦時下のくすんだワード・ローブを排し、幾らかでも魅力ある服を着るよう女性たちを促した年だった。(略)くびれたウエスト、なだらかな肩、そして過ぎ去りし日の女性らしさを強調するジャケットやトップスとともに着用する、たっぷりと布地を使った贅沢なスカートの創作を通して、これを表現しようとした。(略)しかしながら、決してすべてが肯定的に受け入れられたわけではなかった。新しいシルエットは多くの女性に失望感を引き起こし、アメリカでは激しく反対する人びと(少なくとも数千人)が抗議グループを結成した (B:p.162)。
補足:シャネルもディオールのニュー・ルックに反発。なんと71歳になった1954年に、メゾン(maison : ファッション業界では、デザイナーが取りまとめている会社を指す)を再開します。
〇 イヴ・サンローラン (Yves Saint=Laurent) とマリー・クワント (Mary Quant)
1950年代を代表するスタイルのひとつがトラペーズ・スタイル (Trapaze style) で、これは1958年にイヴ・サン=ローランによって発表された。台形のように形作られた服は、もう1つの美学を示した。肩幅を狭くカットし、肩からフレアを垂らすと、ゆったりとした建築的な効果が生まれた。それは、くびれたウエストと、おおきく膨れ上がったスカート(注:ニュー・ルックを指す)から遠く離れた世界だった。トラペーズは、体に密着しないスタイルの1つで、大まかに「シュミーズ」ドレスと称された(略)マリー・クヮント(原文のまま)がこれの変形スタイルを採用し、1960年代ファッションに不可欠の定番となった (B:p.166)。
元来1960年代前半のロンドンの下町の若者の服装だったミニスカート。このスカートは、マナーや慣習、お行儀といったものに反発するもので、これを導入したマリー・クワントが大流行となった (A:p.159)。
補足:2022.12.04付日本経済新聞の展覧会評に「ガブリエル・シャネルは1968年、イヴこそ自分の後継者だと公言している」という文があります。イヴの、体を締めつけないスタイルと男物の要素を女性ファッションに取り入れた点に、シャネルは自分と相通じるものを見出したのでしょう。また、Aのp.159には、ミニスカートのツィッギー (Twiggy) の写真も掲載。当時、ミニスカートといえばツィッギーでした。
〇 クリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランとマリー・クワントの展覧会
今回、「マリー・ローランサンとモード」に出品されないデザイナーについても書いたのは、下記のとおり、2023年に展覧会が開催されるからです。開催地が東京なので鑑賞は難しいと思いますが、同じ年に20世紀を代表するデザイナーの展覧会が、美術館で4つも開催されるので、ご紹介します。
・マリー・クワント展 2022.11.26-2023.1.29 Bunkamura ザ・ミュージアム
URL: マリー・クワント展 | Bunkamura
・クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ 2022.12.21-2023.5.28 東京都現代美術館
URL: クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ | 展覧会 | 東京都現代美術館|MUSEUM OF CONTEMPORARY ART TOKYO (mot-art-museum.jp)
・イヴ・サンローラン展 2023.9.20-12.11 東京・国立新美術館
URL: イヴ・サンローラン展 (ysl2023.jp)
Ron.