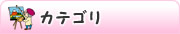名古屋市美術館の展覧会=「写真の都」物語、没後10年、荒川修作―初期平面の仕事 の感想なども
2020年7月、日本経済新聞で杉本博司氏の「私の履歴書」(以下「履歴書」)が連載されました。連載中は「面白い」とは思うものの「どういう切り口で読んだらいいのかわからない」ので、モヤモヤしていました。それが、名古屋市美術館の「写真の都」物語(以下「写真の都」)と特集展示・没後10年 荒川修作―初期平面の仕事(以下「荒川修作特集」)を見たことで「切り口」がつかめたような気になりました。
以下、履歴書と二つの展覧会、双方の感想などを合せて書いてみます。
◆高校生・大学生の写真部、ドキュメンタリー写真とコマーシャルフォト
「写真の都」第Ⅵ章のタイトルは<中部学生写真連盟>――集団と個人、写真を巡る青春の模索。展示されていたのは、主に1966年(昭和41)から1972年(昭和47)までに撮影された写真でした。学生運動を題材にしたものが多く、第Ⅴ章に出品された東松照明《プロテスト》(1969)と同様の、ドキュメンタリー写真に分類される写真です。
2月12日に開催された名古屋市美術館協力会主催の解説会(以下「解説会」)では、担当の竹葉丈学芸員(以下「竹葉さん」)が「学生運動の衰退とともに、学生写真運動も衰退していった」と解説していたのが、印象的でした。
一方、「写真の都」第Ⅵ章が焦点をあてた時代について、杉本博司氏(以下「著者」)は履歴書第8回に「私が大学を卒業する1970年、学園闘争は前年の東大安田講堂の陥落を受けてピークを過ぎていたが、依然大学はバリケードで封鎖されたままだった。(略)そのころ写真の腕は上達していた。高校の写真部から大学では広告研究会、写真部で腕を磨いていた。カリフォルニアのアートスクールに入学審査のため作品を送ってみると、思いがけなく2年飛びで3年からの入学が許可された(略)」と書いています。
著者は1966年から70年まで、高校・大学の写真部に属していました。大学では広告研究会にも属していたということですから、著者がめざしていたのはドキュメンタリー写真ではなく、コマーシャルフォトだったのかもしれません。著者はまた、履歴書第10回に、ニューヨークで職探しをしてプロ写真家の助手になったが、広告写真は性に合わず断念。「現代美術家として出発することを心に決めた」と書いています。
◆福原信三と資生堂宣伝部
コマーシャルフォトといえば1月30日(土)放送のテレビ愛知「美の巨人たち」は1966年(昭和41)に発表された資生堂サマーキャンペーン「太陽に愛されよう」のポスターを取り上げていました。プロデューサーは資生堂宣伝部の石岡瑛子(1970年に石岡瑛子デザイン室として独立)。日本の広告で初めて海外ロケをハワイで行ったポスターで、モデルの前田美波里を撮影したのは横須賀功光。広告業界で話題を呼んだそうです。なお、資生堂宣伝部の前身は福原信三が1916年(大正5)に開設した資生堂意匠部です。
この福原信三については、解説会で竹葉さんが「1921年(大正10)、東京・銀座で資生堂を経営する福原有信の三男・福原信三が、パリ滞在中(1913)に撮影した写真から24枚を選んで「巴里とセーヌ」という写真集を刊行した」と解説していました。
ちなみに、履歴書第15回には、資生堂宣伝部にスタイリストとして勤めた後、美術大学のアート・スチューデンツ・リーグで絵画を学んでいた渕崎絹枝さん(1987年に病気で他界)と親しくなり、結婚を決めたという話が書かれています。
◆荒川修作と論争、河原温からは作家の取り分を聞く
履歴書第12回には1970年代後半のニューヨークで著者と交流した芸術家たちのことが書かれています。
面白かったのは、篠原有司男のロフトで酒に酔って荒川修作と論争した話です。著者は、荒川修作から「写真は小切手だ。小金で買える装飾品でアートではない」と言われたので、「あんたはデュシャンピアンを気取っているが、それはデュシャンに対して失礼だ」と反論したとのことです。なお、反論については、著者は深酔いして覚えておらず、観戦していたアーティストから聞いた話として書いています。
履歴書第10回で、ミニマリズム、コンセプチュアリズムの現代作家として出発することを決意した時、フィラデルフィア美術館に出かけてマルセル・デュシャンの作品を見た、と書いているので、著者はデュシャンピアン(マルセル・デュシャンに影響を受けた、または傾倒している人)を自認しているのでしょう。
篠原有司男と荒川修作の関係については、「荒川修作特集」の会場・常設展示室3に置かれていた作品カードに「1960 篠原有司男、吉村益信らとネオ・ダダイズム・オーガナイザーズ を結成。翌年、渡米」と書いてあったので、納得しました。
また、河原温については、著者が画廊と契約を結ぶ段になり、作家の取り分について尋ねたところ「君の場合は50パーセント、僕の場合には展覧会の前にすべて売れているから70パーセントだよ、と言われた」と書かれています。
作品の値段については、履歴書第13回に、1976年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の写真部に、アメリカ自然史博物館のジオラマを撮った白熊などの作品を持ち込んだ時、写真部長ジョン・シャカフスキー氏から「君はまだ無名だから500ドルで買うことにしよう」と言われたと書かれています。(ネットの「Culture
Power- 杉本博司」で岡部あおみ氏によるインタヴューを読むと、帰りがけに書類を渡されて「普通のアーティストが作品を売る場合って5割引きなんだけど」と言われ250ドルに値切られた、とのこと。それでも、スタジオ兼ロフトの家賃が120ドル(履歴書第13回に掲載)の時代なので大金です)
履歴書第19回には1981年、ニューヨークのソナベンド・ギャラリーで初めての個展を開いた時の話として「劇場のシリーズで、1点1200ドル、数点売れても生活の足しにしかならない」と書かれています。
確かに、当時、荒川修作が著者に言った「写真は小切手だ。小金で買える装飾品でアートではない」という言葉、「小金で買える」という部分については当たっていたかもしれませんね。
◆「現代美術の作品として写真を売る」ということ
解説会で竹葉さんに「第Ⅵ章を見ると、高校生・大学生は写真集を出版して収入を得ているように見えます。当時、写真家が写真で収入を得ようとすると、写真集の刊行というのが一般的だったのでしょうか」と質問したところ、「そうなんじゃないですか」との回答を頂きました。
もちろん、撮影した写真が雑誌などに売れれば、写真家には原稿料が入るわけですが、当時はまだ、プリントした写真を美術品として売り買いするのは、一般的ではなかったような気がします。
これに対して、履歴書によると、著者は現代美術家としてスタートした時から、プリント1点500ドル、1200ドルという方式でプリントを売って収入を得たことが書かれているので、「アメリカの美術界は、当時から違っていたのだ」と認識を新たにしました。
とはいえ、履歴書第20回に、1995年にニューヨークのメトロポリタン美術館(Met)で開催した個展を皮切りに作品が売れるようになり、1778年に開業した古美術商(経緯は履歴書第17回に掲載)をやめて作家活動に専念するようになった、と書かれています。1976年に「ニューヨーク近代美術館の収蔵作家」というブランドを得ても、作家活動に専念できるようになるまでには、様々な苦労をしたのですね。
(参考)「写真の見方」著者:細江英公、澤本徳美 発行所:株式会社新潮社 発行:1986.07.25 の記述
1986年発行の新潮社「写真の見方」は、写真と美術館との関係について、以下のように書いています。
p.47 目的は様々であったが、早くから積極的に写真の収集を行ったのはアメリカ合衆国であった。(略)
写真を独立した芸術作品として意識的に収集するのは、1920年代になってからである。1924年にボストン美術館はアルフレッド・スティーグリッツの作品を永久的なコレクションとして27点購入した。1928年にはニューヨークのメトロポリタン美術館が、スティーグリッツが夫人のオキーフを主題として撮った作品を収集し、1933年には、彼の所蔵する作品を譲り受けている。
しかし、美術館が正式に写真の部門を設け、組織的にコレクションを始めたのは、1940年に写真部門が設立されたニューヨーク近代美術館である。ここが写真の収集を始めたことは、写真が近代芸術の一つとして認知されたことを証明し、アメリカの多くの美術館に影響を与え、写真部門の設置を慣例化するに至ったのである。
世界最大のコレクションを誇る写真部門の国際美術館、ニューヨーク州ロチェスターのジョージ・イーストマン・ハウスが設立されたのは1949年であった。
Ron.