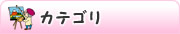名古屋市美術館で開催中の「アドルフ・ヴェルフリ展」のギャラリートークに参加しました。担当は笠木日南子学芸員(以下「笠木さん」)、参加者は34人でした。

◆アドルフ・ヴェルフリ(以下「ヴェルフリ」)って、どんな人?
笠木さんによると「ヴェルフリ(1864-1930)は、日本でいえば江戸時代(幕末)生れの人。父は石工で、彼は7人兄弟の末子。家は貧しく、ヴェルフリが8歳の時に一家離散。ヴェルフリは里子に出されて里親の下で働かされた後、各地を転々とし、1885年、31歳の時に精神病院に収容された。今回の展示は、病院の中で描かれた作品。」とのことでした。
ヴェルフリは、とても悲惨な境遇の人だったのですね。
◆第1章 初期の作品
笠木さんによると「ヴェルフリは、自分を作曲家だと思っており、作品を楽譜と呼んだ。ただし、楽譜は五線譜ではなく六線譜で、初期の作品には音符がなかった。ヴェルフリの特徴は、初期から晩年までスタイルが不変であること。」とのことでした。
確かに、画面を隙間なく直線や曲線、人の顔、丸、ナメクジのような形、文字、数字などで埋め尽くすというスタイルはどの作品にも共通していますね。それにしても、下書き無しで大画面を破綻なく描き切るヴェルフリの才能は大したものだと思います。
◆第2章 揺りかごから墓場まで(1908-1912)
笠木さんによると「第2章の作品が最も色鮮やか。1908年に研修医のモルゲンターラーが赴任して、ヴェルフリの作品を価値あるものと認め、色鉛筆を与えたことによりカラフルな作品が生まれた。ヴェルフリは色彩感覚に優れており、描いているうちに色鉛筆がどんどん短くなって使える色鉛筆が減っていっても、残った色をうまく使い、色彩のバランスが崩れない。”揺りかごから墓場まで“は、世界各地を旅して、お金を稼ぎ、自分の領地を広げるという冒険物語。ただし、文章と絵の内容は一致していない。また、稼いだお金の1973年から2000年までの利息を計算した表もある。」とのことでした。
「物語を書いて、絵も描く。」という行為は、想像の世界に羽ばたき、ヴェルフリの過酷な境遇を忘れさせるもので、彼の生活に欠かせないものであったと分かりました。
◆第3章 地理と代数の書(1912-1916)
笠木さんによると「第3章でヴェルフリは、自分が得た資本財産の利子計算をして、画面を膨大な桁数の数字で埋め尽くすとともに、多くの楽譜を描いている。楽譜のもとになっているのは、教会で聞いた音楽や、教会で見た楽譜、軍隊で聞いた音楽、フォークダンスの曲など。」とのことでした。
たとえ、机上の計算であっても、自分の資産がどんどん増えていくことは楽しいものです。膨大な桁数の数字を書き続けることは、ヴェルフリの生き甲斐だったのでしょう。
◆第4章 歌と舞曲の書(1917-1922)、歌と行進のアルバム(1928-1924)
笠木さんによると「第4章では、絵が減ってコラージュが増えていく。また、神の名の頭文字のアルファベットを装飾的に描き、人の顔や丸、曲線などのモチーフで埋め尽くした作品もある。」とのことでした。
笠木さんは、芸者の写真のコラージュやキャンベル・スープの缶詰のイラストのコラージュがある作品などについて解説。ヴェルフリの美的センスを実感しました。
◆第5章 葬送行進曲(1928-1930)
笠木さんによると「第5章は、言葉と数字の繰り返しで、“16.シェアー.1.ヴィーガ,16.シェアー:1.ギーイガ.16.シェアー:1.シュティーガ,16.シェアー.1.シーイガ,……”というように、ヴィーガ(Wiiiga:方言で「揺りかご」)を、韻を踏んで少しずつ変形させながら、ラップのように繰り返し書いている。」とのことでした。
ヴェルフリは、語呂合わせ等の言葉遊びが好きな人だったのですね。
◆第6章 ブロートクンスト―日々の糧のための作品(1916-1930)
笠木さんによると「“揺りかごから墓場まで”等は自分のための作品で売りに出すことは無かったが、当時、ヴェルフリは売れっ子で、作品を買う人がいた。ブロートクンストは販売用のもので、色鮮やかで分かりやすく、画用紙に描いた作品。額装のような装飾が施され、作家のリルケや精神科医のユングも所蔵していた。」とのことでした。
自分の作品が売れて小遣い稼ぎができたことで、ヴェルフリは大きな自信を得たことでしょう。今見ても、ブロートクンストは可愛いと思います。
◆アドルフ・ヴェルフリの再評価
笠木さんによると「ヴェルフリの死後、1945年にジャン・デュビュッフェが病院を訪れて、ヴェルフリの作品を発見し、Art Brut (アール・ブリュット=生の/未加工の芸術)と名付けて高く評価した。1950年代には、シュルレアリストのアンドレ・ブルトンもヴェルフリを評価。1970年代には、スイス出身のキュレーターのハラルト・ゼーマンがベネチア・ビエンナーレやドクメンタで紹介。ヴェルフリの作品はモダン・アートのアーティストたちを刺激した。」とのことでした。「モルゲンターラーが赴任するまで、ヴェルフリの作品は「価値がない」として捨てられていた。」との解説もありました。
現在、日本経済新聞に、伊藤若冲をはじめとする江戸美術の収集家、ジョー・プライスが「私の履歴書」を書いています。連載の第1回は、若い頃に一目見て思わず買った絵が若冲の作品だったという話でした。江戸美術の収集を進めるうちに、辻惟雄や小林忠といった研究者と知り合い、コレクションの輸送費や保険料をプライスが負担して、江戸美術の展覧会開催に協力したという話もありました。ヴェルフリや若冲の例を見ると、芸術作品が評価されるには審美眼を持った人物との出会いが必要なのだな、と思いますね。
◆最後に
この展覧会が始まるまで、アドルフ・ヴェルフリという人の名前すら知らなかったので、ギャラリートークも参加者は少ないだろうと思っていたのですが、意外に人数が多かったのでびっくりです。ギャラリートークでは、不思議な魅力のある作品を数多く見ることが出来ました。

解説してくださった笠木学芸員、ありがとうございました!
Ron.