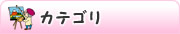名古屋市美術館で開催中の「ザ ベスト セレクション」(以下「本展」)のギャラリートークに参加しました。台風25号の進路によっては「中止」もあり得ましたが、台風は日本海を進み、当日は快晴。無事、開催されました。晴れ女(晴れ男?)さん、ありがとう。
担当は、保崎裕徳学芸係長(以下「保崎さん」)と角田美奈子学芸員(以下「角田さん」)。参加者は70人。参加人数は多いもののグループ分けはありません。会場がゆったりしており、ポータブルのワイヤレス拡声装置で隅々まで声が届くため、70人全員が一緒に動くこととなりました。壮観でしたね。
以下は、保崎さんによるギャラリートークの概要です。なお、(注)は私の補足。主な作品については作者名・作品名・制作年に加えて作品解説の「見出し」を記載しました。本展では「主要作品」と「知られざる傑作」に詳細で気の利いた解説が添えられています。解説本文は会場で見ていただくこととして、ここでは「見出し」だけを紹介します。
◆本展の概要など
◎名古屋市美術館の収蔵品は開館後30年間で6,278点に
名古屋市美術館は1988(昭和63)年4月22日に開館し、今年、開館30周年を迎えました。ただし、コレクションの収集は1983(昭和58)年から始めています。収集の結果、収蔵品の点数は2017(平成29)年度末の時点で6,278点となりました。収蔵品の点数は1998(平成10)年度末で2,106点、2008(平成20)年度末で4,332点ですから、10年間で2,000点ずつ増やした勘定になります。なお、厳しい財政事情のため2005(平成17)年頃から購入による収集が難しくなりました。最近の収集は、ほぼ寄贈によるものです。
「購入が難しい」と申しましたが、開館30周年を記念して団体・個人から寄付をいただき「夢・プレミアムアートコレクション」として藤田嗣治《ベルギーの婦人》を購入することができました。地下1階の常設展示室で公開していますので、お越しください。
◎「外せない作品」に「なかなか紹介されなかった作品」「知られざる傑作」を交えて展示
本展は開館30周年記念展なので「外せない作品」を展示することは当然ですが「なかなか紹介されなかった作品」「知られざる傑作」も交えて展示しました。
また、オーソドックスに「4つの収集方針」= ①エコール・ド・パリ、②メキシコ・ルネサンス、③郷土の美術、④現代の美術の順に、主に地元作家の作品を展示しています。
◆エコール・ド・パリ
(主な作品)
・マルク・シャガール《二重肖像》1924年
二度目のパリで手にした穏やか日々、束の間の幸福を永遠に記録した傑作《二重肖像》。
・アメデオ・モディリアーニ《おさげ髪の少女》1918年頃
おさげ髪の少女のモデルについて(本文より:日本人画家の平賀亀佑の妻、マリー?)
・キスリング《マルセル・シャンタルの肖像》1935年
見よ、この眼力(めぢから)圧倒的な存在感!画家はモデルの魅力のとりことなった。
・モーリス・ユトリロ《ノルヴァン通り》1910年
あの場所は今?ユトリロが描いたパリ、ノルヴァン通り。
・ハイム・スーチン《農家の娘》1919年頃 → 代替品《鳥のいる静物》
(ギャラリートーク)
エコール・ド・パリは1927年にフランスに渡った地元作家・荻須高徳(おぎす・たかのり)に関係するコレクションです。荻須高徳と同時代のエコール・ド・パリの作家、シャガール、スーチン、モディリアーニ、キスリング、ユトリロなどの作品を展示しました。
キスリング《マルセル・シャンタルの肖像》は2001年に購入。エコール・ド・パリのタブローとしては、これが最後の購入品でした。藤田嗣治《ベルギーの婦人》はそれ以来、十数年ぶりに購入できた作品です。マルク・シャガール《二重肖像》は高すぎて購入できないため、中部電力株式会社が買い上げ、名古屋市に寄贈された作品です。
ハイム・スーチン《鳥のいる静物》は作品リストにはありません。リストには《農家の娘》が掲載されています。ランス美術館に貸し出されていたのですが、台風21号で関西空港が被害を受け、搬入が遅れています。10月下旬から11月初旬には展示できると思います。
アメデオ・モディリアーニ《おさげ髪の少女》は1986年に購入した作品。3億6千万円の価格は当時の日本の公立美術館で最高の購入金額でした。しかし、1989年に大阪市がモディリアーニ《髪をほどいた横たわる裸婦》を、1990年に愛知県美術館がグスタフ・クリムト《人生は闘いなり(黄金の騎士)》を購入するなど《おさげ髪の少女》を上回る高額な絵画の購入が相次ぎ、《おさげ髪の少女》の記録は抜かれました。(注:角田さんから「《黄金の騎士》は《おさげ髪の少女》より、うんとサイズが大きい(ので比べものにならない)」という声がかかりました)
モーリス・ユトリロ《ノルヴァン通り》は1992年に購入した高額作品です。(注:購入契約にあたり市議会の議決が必要な価格(八千万円)を超える収蔵品は《おさげ髪の少女》と《ノルヴァン通り》の2点のみです。《二重肖像》は高額作品ですが、寄贈なので市議会の議決は不要でした)
◆メキシコ・ルネサンス
(主な作品)
・岡本太郎《明日の神話》1968年
《明日の神話》下絵の寄贈と修復 (本文:日系移民 小栗順三氏のメキシコの自宅)
・フリーダ・カーロ《死の仮面を被った少女》1938年
人の心を打つ作品と人生 日本でフリーダの絵が見られるのは名古屋市美術館だけ。
・マリア・イスキエルド《旅人の肖像(アンリ・ド・シャティヨンの肖像)》1935年
シュールとは夢ではない、それはもう一つの確かな表現なのだ。
・ダヴィッド・アルファ・シケイロス《奴隷》1961年
獄中でほとばしる想像力。 シケイロスの熱いメッセージ
(注:「《奴隷》裏面のシケイロスによる文章(要約)」も掲示されています)
(ギャラリートーク)
岡本太郎《明日の神話》は高さ5.5メートル、長さ30メートルの巨大な壁画で、2008年からJR山手線渋谷駅と渋谷マークシティーの京王・井の頭線渋谷駅を結ぶ連絡通路に展示されています。これは1968年にメキシコ市のホテルに飾る壁画として依頼されたもので、岡本太郎は大阪万博の《太陽の塔》と並行して制作していました。
本展に展示しているものは、その下絵。メキシコ市のホテルのオーナーに岡本太郎を紹介した日系移民の小栗順三氏の自宅に保管されていたものです。1999年に「下絵がある」という情報提供があり、小栗順三氏の奥さんのふじ子氏(順三氏本人は既に死亡)と岡本太郎氏の幼女・岡本敏子氏の連名で名古屋市美術館に寄贈されたものです。個人の住居に保管されていたことから作品には亀裂や絵の具の剥落があり、寄贈を受けた後に修復を施しています。寄贈までの経緯については「アート・ペーパー」49号と50号に山田諭氏が、修復の経緯については「紀要」11号に角田美奈子氏が寄稿しています。
メキシコ・ルネサンスの展示にフリーダ・カーロは欠かせませんが、イスキエルドの作品も紹介したいと思い、展示しました。シケイロスは、作品の裏面に書かれたメッセージも紹介したかったので、特別な展示方法をしています。(注:表・裏の両面を見ることが出来るよう、通路の中央に台を置いて展示しています。作品の裏(メッセージが書かれている面)にはアクリルカバーがあるのに、表(絵が描かれた面)にカバーはありませんでした。なお、本展の展示作品には、全て保護カバーがありません。なので、照明などの映り込みを気にすることなく鑑賞できます)
メキシコでは1910年に革命が始まりました。戦争終結後の1920年当時、メキシコの民衆(メスティーソ)の80パーセントは文字が読めないという状況だったため「メキシコの歴史や将来ビジョンを示す」という目的で壁画運動が始まりました。多くの人がメッセージを受け取ることができるよう、大きな画面に分かりやすい絵画が描かれました。シケイロス、リベラ、オロスコの三人が代表的な作家です。

作品を囲んでの解説
◆郷土の美術
◎東山動物園猛獣画廊壁画
・太田三郎《東山動物園猛獣画廊壁画 No.1》1948年
・水谷 清《東山動物園猛獣画廊壁画 No.2》1948年
・宮本三郎《東山動物園猛獣画廊壁画 No.3》1948年
(ギャラリートーク)
この3点は1997年に収蔵して以来、一度も展示したことがない作品です。傷みがひどいためこれまで展示を見送ってきました。本展では「貴重な作品だ」というメッセージを伝えるため、やむなく修復されていない状態で展示しています。
第2次世界大戦中、軍から猛獣を処分するよう指示が下され、東山動物園ではヒグマを毒殺、ライオンを絞殺しました。その後、射殺や食料不足、暖房不足などにより猛獣は激減。戦後、動物園を再開した時、動物30頭ほどという状態でした。(注:ゾウ2頭については、有名な「ぞう列車」のお話がありますね)
そのため、1948年中京新聞社が3人の画家に動物の生態を描いたジオラマの制作を依頼。旧カバ舎を「猛獣画廊」としてジオラマを展示することになりました。作品の解説には「猛獣畫廊」開きの式の模様を伝える紙面のコピーも掲げています。
東山動物園猛獣画廊壁画は、美術が社会の役に立った貴重な事例として展示しました。次に展示できるのが何時になるのかは分かりません。
◎郷土の日本画
(主な作品)
・渡辺幾春(わたなべ・いくはる)《若き女》1922年
浮世絵好きの作者だからこそ描ける、センチメンタルなムード。
・喜多村麦子(きたむら・ばくし)《暮れ行く堀川》1929年
あの場所は今? 喜多村麦子が描いた堀川。
・横山葩生(よこやま・はせい)《磯》1934年 (注:解説なし)
・大島哲以(おおしま・てつい)《終電車》1967年
半獣半人たちの奇怪な行動。終電車は何処へ行く。
(ギャラリートーク)
日本画の部屋は作品保護のために暗くせざるを得ません。暗い中でも作品が見やすくなるよう、照明にこだわりました。白いLEDを何本も使っています。
大正時代の渡辺幾春、横山葩生は、いずれも帝展入選作です。喜多村麦子の《暮れ行く堀川》には木橋を描いたものと石橋を描いたものがあります。これまでは木橋を描いたものを展示することが多かったのですが、本展では石橋を描いたものを展示しています。昭和初期の制作ですが、大正前期の風景を描いたものです。洋画の部屋に展示している西村千太郎《納屋橋風景》は昭和初期の風景ですから、二つの作品の風景には15年の開きがあります。
展示ケースには川合玉堂と戦後の前衛的な日本画・中村正義、星野真吾らの作品が同居しています。作品の傾向が全く異なるので、その間をカーテンで仕切りました。
大島哲以は名古屋市生まれの日本画家です。金属の箔を貼った上から、体は人で頭が鳥の女たちと、体は人で頭が山羊の男たちを描いています。終電車の中なのに、七輪でカエルを焼く女がいて、煙が車内に充満しています。また、上からはアリナミンの瓶から錠剤が、コーラの瓶から液体がこぼれています。花鳥風月ではなく社会風刺を主題にした作品です。
前衛的な作品の次には、前田青邨、平松礼二、田淵俊夫の作品を展示しました。
(注:中村正義や前田青邨、平松礼二、田淵俊夫の作品には「解説」がありません。「良く知られた作家や作品には、通常の展示と同様に解説はつけない」ということのようですね)
◎郷土の洋画
(主な作品)
・横井礼以(よこい・れいい)《蜜柑を持つK坊》1922年
着物に前掛け姿のK坊 フランス流のモダン・スタイルで登場。
・西村千太郎《納屋橋風景》1930年
まるで名古屋の「セーヌ河畔」。ハイカラな名古屋の一面を捉えた《納屋橋風景》。
・市野長之助《バザーの楽器店》1929年
明治44年、栄にできた ショッピング・モール、「中央バザー」。
・宮脇晴(みやわき・はる)《夜の自画像》1919年
この時、なんと17歳。名古屋市立工芸学校在学中の宮脇晴。
・遠山清《マノハラ水浴》1927年
洋画で「仏画」を描く斬新な試み。描いたのは新明小学校の先生。
・富澤有為男(とみざわ・ういお)《姉》1928年
帝展入選者にして芥川賞作家、富澤有為男の稀有な才能。
(ギャラリートーク)
洋画の部屋では主に、脚光を浴びていない作家・作品を紹介します。
宮脇晴は17歳の時の日記に「夜、自画像を描く」と書いているので17歳の時の作品だと思われます。なお、彼は翌年、帝展に初入選しています。
これまで、郷土の美術では主に「愛美社」「サンサシオン」の作家を紹介しており、横井礼以や彼が創設した緑ケ丘中央洋画研究所で学んだ西村千太郎、市野長之介はあまり取り上げていません。横井礼以《蜜柑を持つK坊》はフォーヴィスム風。西村千太郎《納屋橋風景》は佐伯祐三風で大正モダンの雰囲気があります。《納屋橋風景》で、西村千太郎は「パリのように見せる」ために、あったはずのバルコニーを隠すなどの工夫を施しています。バルコニーの外にはどんな工夫をしているでしょうか。(注:質問に答えて「電線がない」との声がありました)その通りです。外には、市電の線路も隠しています。市野長之助が描いたショッピング・モール「中央バザー」は現在の名古屋三越の北側にありました。
遠山清は、帝展入選を目指した同人「サンサシオン」加わっていた画家で、《マノハラ水浴》はテンペラで描いた仏画です。「他人と同じことをしていては目立たない」と思って描いたのでしょうか。
富澤有為男《姉》は水彩画のように見えますが、油絵です。彼は東海中学校卒業時に「文学」を目指しましたが父親は反対。母親が出した妥協案が「絵画」でした。母親の従妹に洋画家の岡田三郎助がいたことから東京美術学校に通うことになったのですが、半年で退学。新愛知(中日新聞の前身の一つ)の記者となりましたが、その後、記者をやめて上京し、「文学」と「絵画」の二足の草鞋を履きます。「サンサシオン」の会員となって展覧会に出品。1929年から1930年までフランスに留学して絵画を学んだものの留学先のパリでは映画が大流行で「絵画は時代遅れ」と思ったため、帰国後は小説を執筆。ただ、第4回芥川賞(注:正式には「芥川龍之介賞」)を受賞した小説「地中海」の主人公は画家で舞台はパリと南フランス。留学経験は小説に生かされたようです。
◆現代の美術
(主な作品)
・河原温《カム・オン・マイハウス》1955年、《私生児の誕生》1955年
時代の閉塞感が画面を歪める?!戦後の日本社会を鋭く見つめた、若き日の河原温。
・桑山忠明《無題》1965年
アメリカ現代絵画の第一線で活躍する桑山忠明 大学時代は意外にも日本画専攻。
・荒川修作《35フィート×7フィート6インチ、126ポンド No.2》1967-68年
10.7m×2.3m、47kg。タイトルの数字が意味するものは?
・赤瀬川原平《復讐の形態学(殺す前に相手をよく見る)》1963年
旭丘高校美術科出身、前衛画家赤瀬川原平の渾身の力作 130倍に拡大模写した千円札。
・藤本由紀夫《TABLE MUSIC》1987年
《TABLE MUSIC》の鑑賞方法
① この作品には触ることができます。やさしく触れてください。
② 巻ききらないよう注意しながら、お好みのネジを巻いてください。
③ 新しくできあがる音楽に耳を傾けてください。
(ギャラリートーク)
名古屋市美術館で現代美術の主要作家は郷土出身の河原温、荒川修作と桑山忠明です。また、荒川修作と旭丘高校美術科の同級生・赤瀬川原平の作品も収集しています。赤瀬川原平は尾辻克彦のペンネーム(注:本名は赤瀬川克彦)で執筆した「父が消えた」により芥川賞(注:1980年下半期の第84回芥川賞)を受賞しています。名古屋市美術館が作品を収蔵している作家のうち、何と2名が芥川賞を受賞しています。
河原温は「Todayシリーズ」が有名で、どの美術館も収蔵しています。なので、本展では河原温がニューヨークに渡る前の1955年に描いた「変形キャンバス」の《カム・オン・マイハウス》と《私生児の誕生》を展示しました。「変形キャンバス」の作品は、名古屋市美術館以外では東京国立近代美術館が《孕んだ女》を、大原美術館が《黒人兵》を所蔵しています。《カム・オン・マイハウス》の画面中央に逆さまになった女性が描かれています。よく見ると女性は右腕を伸ばしてビンをつかんでいるのですが、手の平は左手のもの。ビンの中身が上手く注げません。大原美術館所蔵の《黒人兵》と合わせてみると、戦後の社会問題に対して鋭い批判を投げかけていたことが分かります。
荒川修作の作品は何回も展示しているので今回は解説しません。桑山忠明《無題》は「システミック・ペインティング展」出品作で、クールな抽象画。歴史的価値のある作品です。
藤本由紀夫は名古屋生まれの作家で《TABLE MUSIC》は常設展に2回ほど展示しています。18個のオルゴールを取り付けたテーブルです。(注:オルゴールは金属の円筒に取り付けられたピンが、長さの違う櫛状の金属版(櫛歯)を押し上げて弾くことにより曲の演奏を行う装置です。櫛歯の一本一本が一つの音階に対応しています)18個のオルゴールは、それぞれが一つの音程しか出せないように、他の櫛歯を折り曲げています。運よく18個のオルゴールが全て同調すれば「枯葉:英語”Autamn Leavs”、仏語 “Les Feuilles Mortes”」が演奏されますが、ほとんどの場合は別の曲になります。
◆最後に
参加者からは「こんな作品があるなんて知らなかった」「名古屋市美術館のコレクションの質の良さを再認識した」「こんなに面白いなら、これからも定期的にベスト・セレクション展を開催してもいいのではないか」「東山動物園猛獣画廊壁画は素晴らしい。修復費用を夢・プレミアムアートコレクションで集めてはどうか」などの声が聞かれました。
「常設展の延長だから」と、あまり期待していなかった人が多かったようですが、予想は大きく外れ「見ごたえのある展覧会」となりました。展示室を歩くと微かに《TABLE MUSIC》の演奏が聞こえるのも、心地良いバックグラウンド・ミュージックです。
地下1階では「名品コレクションⅡ」が同時開催されています。今回のギャラリートークでは鑑賞できませんでしたが、「名品コレクションⅡ」では「エコール・ド・パリ」の女性像ばかり集めるなど面白い展示があります。「ザ ベスト セレクション」と「名品コレクションⅡ」は「二つでひとつ」。二つ合わせて鑑賞することをお勧めします。
常設展示室3で開催中の「名古屋市庁舎竣工85年 建築意匠と時代精神」も「一見の価値あり」です。
Ron.