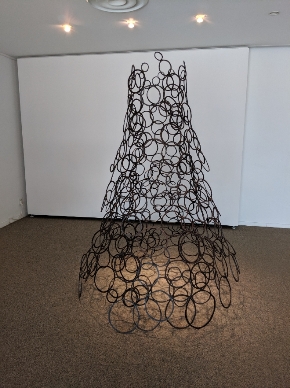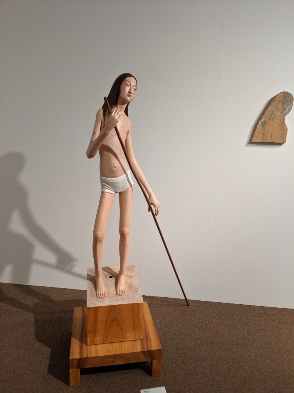◆「みんなのミュシャ」名古屋展のチラシに印刷された少女
あいちトリエンナーレで賑わっている名古屋市美術館に「みんなのミュシャ」(2020.4.25~6.28)のチラシが置いてありました。会期などが印刷されたチラシの表面には、衣装をなびかせる少女が、裏面には夢見るような表情の少女が描かれています。表面の作品はアルフォンス・ミュシャ《舞踏―連作(四芸術)より》(部分)、裏面は《モナコ・モンテカルロ》(部分)。どちらもピンナップしたくなる作品です。
◆「新美の巨人たち」(2019.9.7)「今日の一枚」は《モナコ・モンテカルロ》でした
9月7日放送のテレビ愛知「新美の巨人たち」、「今日の一枚」はアルフォンス・ミュシャが制作した鉄道会社のポスター《モナコ・モンテカルロ》(1897)でした。当日朝刊のテレビ欄には「鉄道のポスターなのに列車を描かない深い訳」という説明が付いていました。
番組で旅人・要潤さんが向かったのは、東京・渋谷のBunkamuraザ・ミュージアム。美術館に向かう途中「要潤さんは、ミュシャの《黄道十二宮》(1896)を持っています」と紹介され、「ミュシャの作品とは知らず、きれいだったから買いました」と答えていました。
《モナコ・モンテカルロ》は展示の後半にあり、「ミュシャの黄金期、37歳の時の作品。モナコ公国の中心地モンテカルロを紹介するPLM鉄道のポスターで右下には小さく、往復チケット、周遊チケット、家族旅行チケット、16時間の豪華鉄道旅行、と印刷されています」「また、この絵には仕掛けがあり、第一は美女を囲む花輪で、それはキリストの光輪。人物を円で囲むことで、その人物に格調の高さと神々しさが生まれる」との解説がありました。第二の仕掛けは緻密な描きこみで、「ミュシャと同時代のロートレックはポスターを芸術の域に引き上げた画家で、単純化した構図を少ない色数で描いています。それに対し、ミュシャが描いたポスターの克明な描写は、当時としては異例の表現でした」との解説。第三の仕掛けは「視線の誘導」で「《モナコ・モンテカルロ》では左下の花輪から延びる茎で少女の顔へ、次に少女が見ている ”MONACO・MONTE-CARLO” という文字に視線が導かれます」と、解説がありました。
番組では、この「ミュシャのスタイル」を借りて、作家の「べつやくれい」さんが《うどんを祝福する要潤》(2019)を制作するというシーンもあります。出来上がった作品は、番組のホームページが紹介しているとおり、格調高く神々しいものです。べつやくれいさんは「ミュシャの描きこみはすごい」と話していました。
また、広告の専門家・箭内道彦さん(東京芸術大学)が登場して「少女の背景にコート・ダジュールの海岸線とカジノが描かれているが、よく見ないと分からない。ミュシャは、直接的な描写ではなく、暗喩で『気分』を描いた。『そうだ 京都 行こう』を先取りしたポスターとも言える。花輪は汽車の車輪、茎は鉄道線路で、鉄道旅行の楽しさを伝えているという説明が一般的だが、花輪はルーレットなのでは等、いろんな読み方ができる。ミュシャの真似はできそうで、できなさそうで、できる」という解説がありました。
以上のほか「黒田清輝が日本にミュシャを紹介。その教えを受けて三越呉服店のポスターを描いた杉浦非水(すぎうら・ひすい)を始めとして、日本のグラフィック・デザインはミュシャの影響を受けてきた」という説明もありました。番組のURLは、下記のとおりです。 https://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/backnumber/index.html?trgt=20190907
◆「みんなのミュシャ Special」(カドカワエンタメムック)2019.7.29 株式会社KADOKAWA発行 現在、書店の店頭には数種類の「みんなのミュシャ」関連書籍が並んでおり、たまたま手に取ったのが、この本です。「ぶらぶら美術・博物館 プレミアムアートブック/特別編集」という副題のとおり、山田五郎が「みんなのミュシャ ミュシャからマンガへ-線の魔術」を解説した本です。おぎやはぎも登場します。展覧会の構成に合わせた作品紹介に加えて「展覧会に展示されるマンガ家プロフィール」「ミュシャと世界・美術のヒストリー」「ミュシャにまつわるキーワード」「山田五郎×みうらじゅん対談」など、肩の凝らない記事ばかりです。表紙が《ヒヤシンス姫》、表紙裏の広告が《黄道十二宮》、中表紙が《ジスモンダ》、見開きページが《舞踏―連作(四芸術)より》(部分)と《モナコ・モンテカルロ》(部分)という構成。ミュシャのポスター・装飾パネルというと、この5作が代表作ということなのでしょうか。
なお、「ミュシャと世界・美術のヒストリー」を読むと、ミュシャは1928年、68歳の時にプラハ市に移り、《スラブ叙事詩》全20点をプラハ市に寄贈することを発表。1939年、78歳の時にドイツがチェコスロバキア共和国に侵攻した際、ゲシュタポに拘束され、5日間の尋問ののち釈放されるが健康状態が悪化し、7月14日、プラハで死去(注1)、ということが分かります。
注1:ゲシュタポが拘束したのは「ムハ(注2:ミュシャはフランス語の読み方。チェコ語ではムハ)の絵画は退廃的で、チェコの民族自決を促す危険なものというのが理由だった。そのため、ナチスの占領中は、彼の作品を展示することがいっさい禁止された」(「図説 プラハ 塔と黄金と革命の都市」ふくろうの本 2011年1月30日発行 著者 片野 優・須貝典子 発行所 河出書房新社 より)
◆Bunkamuraザ・ミュージアムのホームページ
内容は、PR動画のほかに「みどころ」「章解説」などです。
「みどころ」では、「みどころ3 こんなところにもミュシャの影響が?」のアルフォンス・ミュシャ《ジョブ》(1896)と、その色を変えたロック・コンサートのポスター(1966)の比較や、「みどころ4 文芸誌のデザインからマンガまで――日本で生き続ける“ミュシャ”」のアルフォンス・ミュシャ《黄道十二宮》(1896)と藤島武二『みだれ髪』(与謝野晶子)の表紙との比較が面白いと思いました。
「章解説」は、Section1からSection5までの各章ごとの解説です。なお、《モナコ・モンテカルロ》の図版はSection5で紹介しています。Section5には、また「ミュシャは近代の女性たちの内面と身体を表現するアイコンとして、この国の文化史の中にある」という文がありました。展覧会ホームページのURLは、下記のとおりです。 https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/19_mucha/
◆最後に 「みんなのミュシャ」が名古屋市美術館に巡回するのは、2020年4月25日(土)~6月28日(日)と半年以上も先のことですが、東京展開催中ということもあり、展覧会の情報は書籍やインターネット等であふれていますので御紹介いたしました。
なお、BS日テレ「ぶらぶら美術・博物館」では、去る8月13日(火)にBunkamuraザ・ミュージアムの「みんなのミュシャ」を紹介ずみです。とはいえ、できれば来年の名古屋展開催時には名古屋地区で「ぶらぶら美術・博物館」の再放送を実現していただきたいですね。
Ron.