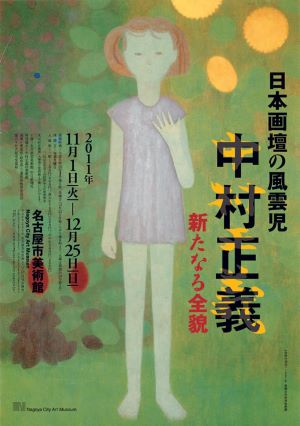7月28日(火)から30日(木)まで中日新聞・県内版に、岡崎市美術博物館で開催中の「マイセン動物園展」の紹介記事が連載されていたので、早速行ってきました。平日ながら、恩賜池に臨む駐車場は満車に近い状態。県内の新型コロナウイルス新規感染者が急増しているため「展覧会場は3密状態か?」と怖くなりました。しかし、よく見ると、ノルディック・ウォーキング用のスティックを持参するなど、運動目的の人が何人もいたので少し安心しました。
動物と神話の人物を組み合わせた作品が多数
「第1章 神話と寓話の中の動物」には、神話に出てくる神や天使、鳥、馬、ライオンなどを組み合わせた作品が並んでいます。白磁の滑らかな肌、頬の薄紅色、色鮮やかな衣服など、どこをとっても「どうやって作ったのだろう?」と思われる美しい作品の数々でした。作品リストの制作年には「1820-1920年頃」と書いてあります。原型製作者であるヨハン・ヨアヒム・ケンドラーの生没年は1706-1775年ですから、彼の原型を元に、後日制作したということでしょうね。
会場の最後「映像コーナー」で上映している動画によれば、ヨハン・ヨアヒム・ケンドラーは彫刻家。マイセン磁器の発明者ヨハン・フリードリッヒ・ベットガー(1682-1719)、絵付師のヨハン・グレゴリウス・ヘロルト(1696-1775)と並び、マイセン磁器を牽引した人物です。マイセン磁器の特色は、石膏の原型で型取りした複数の部材を貼り合わせて複雑なフォルムを造形するところにあります。部品を石膏の型から取り出し余分な所を削って貼り合わせる手の動きを見て「展示されていた作品はどれも、長時間にわたる精緻な作業の結晶だ」と感じました。
繊細で豪華絢爛な器の数々

「第2章 器に表された動物」の圧巻は《スノーボール貼花装飾蓋付昆虫鳥透かし壺》。展覧会のチラシの図版にも使われていますが、壺の全面に石膏原型で型取りした小さな花を貼り付けた上に、鳥や昆虫、カエル、蔦のような植物を貼り付け、しかも壺の下部には透かし彫りが施され、中に黄色い鳥が居るという、気の遠くなるような手間をかけて作られた壺です。
柔らかなフォルムの動物たち

「第3章 アールヌーヴォーの動物」になると、動物の雰囲気が変わってきます。ヨハン・ヨアヒム・ケンドラーはバロック期の彫刻家ですが、第3章は「アールヌーヴォー」様式の作品。第1章、第2章の作品は、権勢を誇るためのものですが、第3章は身近に置いて楽しむもの。制作目的が全く違うのですね。《二匹の猫》は、可愛かったですよ。
常滑焼のような炻器(せっき)の動物も
「第4章 マックス・エッサーの動物」には《カワウソ》など、ベットガー炻器で制作した動物やマスクが並んでいます。炻器は釉薬をかけず高温で焼成した陶器で、日本の常滑焼や備前焼にあたるものです。土の風合いを生かした、素朴で味わいのある作品でした。
最後に
ノルディック・ウォーキングに向かう人の会話に耳を澄ますと「ウォーキングが終わったら、展覧会を見て帰りましょうか」という声が聞こえてきました。コロナ禍で不安の増す毎日ですが「マイセン動物園展」は一服の清涼剤になりました。会期終了予定は9月13日(日)です。
Ron.