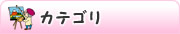コロナ禍で延期されていた「ボイス+パレルモ」(以下「本展」)が、ようやく開催されました。年間パスポートも再開したので、3000円払い、年間パスポートを使って会場に入りました。入口は、1階・展示室8にあります。順番に展示を見ながら3階に行くと、展示室2~4では「コレクション:ドイツと日本の現代美術」(以下、「コレクション展」)を開催していました。コレクション展を見た後、階段を降りて展示室5に入ると本展の展示。本展とコレクション展は一体化していたのです。
1F:展示室8
プロローグ
ヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys、以下「ボイス」)とブリンキー・パレルモ(Blinky Palermo、以下「パレルモ」)が写った写真《プリンキーのために》を展示しています。
1 ヨーゼフ・ボイス:拡張する彫刻
最初に映像作品が2点。《シベリア横断鉄道》(1970)と《ユーラシアの杖:82分のフルクソム・オルガヌム》(1968)でした。いずれも、ボイスが登場するパフォーマンスです。《シベリア横断鉄道》では毛皮のコートを着用し、裏返したキャンバスに向って何かしています。《ユーラシアの杖:82分のフルクソム・オルガヌム》ではベストを着用して、部屋の隅の床に脂肪(ワックス)を塗ったり、柱を立てたり、壁に立てかけたりしていました。また、映像の中で使用されたと思われる、フェルトで包まれた木材(断面はL字型)と鉄棒も展示しています。このほか、折りたたんだフェルト、懐中電灯、脂肪を載せたソリや、鉛筆の描きこみのある箱など、「彫刻」の概念には収まらない作品ばかりで面食らいました。豊田市美術館のコレクション《ジョッキー帽》は「帽子のつばを切り取ってジョッキー帽の形に仕立てた」ものだ、ということも知りました。
2 パレルモ:絵画と物体のあわい
パレルモの作品は、キャンバスを二色に塗り分けたものや単純な線画などです。こういった作品は、いわゆるミニマル・アートに分類されるのでしょうか?
3 フェルトと布
フェルト製のスーツ、丸めたフェルトなど、フェルトを使った作品が並んでいます。
4 循環と再生
銅製の箱が幾つも並んで、銅のテープで繋がっている《小さな発電所》や旅行カバンの中にマギーソースのビンが収まっている《私はウィークエンドなんて知らない》、ガラス製のメスシリンダーに造花の赤いバラを挿した《直接民主主義の為のバラ》などの作品が並んでいます。
1F:展示室6 5 霊媒的:ボイスのアクション
マンモスの化石の前で立っているボイスの写真《芸術=資本》には迫力ありました。また、ショベルや鎌などをケースに納めた《ヴィトリーヌ:耕地の素描》については「物を並べるだけでも作品になるんだな」と、思わず納得してしましました。
1F:展示室7 6 再生するイメージ:ボイスのドローイング
ドローイングが並んでいますが、《あるヒロインのためのバスタブ》は錆びたブロンズ製のバスタブ(ミニチュア)の中に、ハンドルのついた携帯電熱器を入れた作品でした。他にも4冊の本が、作品《「西洋人プロジェクト」(1958)》の一部として展示されています。
2F:展示室1
8 流転するイメージ:パレルモの金属絵画
アルミニウムを単色で塗ったり、2色、3色に塗り分けたりする作品が並んでいました。
エピローグ
「帽意子」「墓異州」「暮椅子」と、漢字を縦書きした黒板が展示されていました。さらに、「帽」にはBo、「意」にはi、「子」にはSuという文字が右に書かれ、「帽」と「子」を繋げてhetと書いています。漢字はどれも「ボイス」を日本風に表記したもの。「帽意子」にはトレード・マークの「帽子」が隠れているということなのでしょうね。ユーモアを感じます。
3F:第2展示室 コレクション:ボイス+パレルモ以前:1950‐60年代のデュッセルドルフ
ボイスがデュッセルドルフ芸術アカデミーの教授に就任したのは1961年。展示室2では、戦後ドイツの前衛的な表現の一大拠点となっていた1950-60年代のデュッセルドルフで活動していた作家の作品を展示しています。ギュンター・ユッカー《変動する白の場》は板に無数の釘を打ち付けて白く塗った作品。昨年公開された映画「ある画家の数奇な運命」のデュッセルドルフ芸術アカデミーには、木の板に釘を打ち付けて作品を制作している学生・ハリーが登場していました。
3F:通路~展示室3 コレクション:ドイツの現代美術
通路に展示されているのは合板を3枚重ねた作品、イミ・クネーベル《蓄光サンドイッチ》No.1~No.3でした。実際に光を放つのではなく「光を放つことを想像しながら鑑賞する作品」とのことです。
展示室3のイミ・クネーベル《DIN規格1 B1-B4》を見て、展示室1にあったパレルモの金属絵画を思い出しました。展示室3の床には、平べったくて白く四角い物体が置かれています。ヴォルフガング・ライプ《ミルクストーン》という作品で、表面は牛乳で覆われています。この牛乳については「毎日取り換えている」という説明がありました。
3F:展示室4
コレクション:ドイツと日本の現代美術
日本の現代美術では、ボイスが生まれた1921年、パレルモが生まれた1943年、それぞれ同世代の作家を取り上げていました。ボイスと同年代の作家のうち、水谷勇夫(1922-2005)と三上誠(1919-1972)は豊橋市美術博物館のコレクション展「从会の作家たち」でも見ました。パレルモと同年代の作家としては、小清水之漸(1944- )などの作品が展示されています。
コレクション:師弟関係-まなぶ? まねる?
エゴンシーレとクリムト、大澤鉦一郎と宮脇晴といったコレクション展の常連は、このコーナーで展示されています。さて、小堀四郎、宮脇綾子も登場しますが、「師」は誰でしょう?
2F:展示室5 7 蝶番的:パレルモの壁画
壁画そのものを展示することは無理なので、壁画のデザイン画と壁画の写真を展示していました。
感想など
巡回展「ボイス+パレルモ」だけでなく「コレクション:ドイツと日本の現代美術」も連続して鑑賞することができるので、得した気分になりました。7/10~9/20に「モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて」が開催されますから、年間パスポートが復活したのも朗報です。
Ron.