「クリムト展 ウィーンと日本1900」(以下「本展」)が開幕したので、JRと愛知環状鉄道(以下「愛環鉄道」)を乗り継いで豊田市美術館まで出かけました。今回、気持ち良かったのは愛環鉄道でも交通系ICカード(MANACA、TOICA等)が使えるようになったことです。切符を買う手間が不要なので、スムーズな乗り換えができました。
美術館に近づくと、平日の午前中というのに満車に近い状態の駐車場が見えてきました。そして、美術館のエントランス通路には巨大なテント。長い行列ができるのを見越して設置したのですね。当日、行列はありませんでしたが展示室の中には多くの人がいて、本展の人気の高さを実感しました。ただ「人が多い」といっても身動きが取れないほどではないため、作品に近づいてじっくり鑑賞することはできました。
◆展覧会の構成と見どころなど 本展は「Chapter1.クリムトとその家族」から「Chapter8.生命の円環」までの8章で構成されています。
◎Chapter1.クリムトとその家族 ボヘミア出身の金工氏師・エルンストの長男としてクリムトが生まれたということから、Chapter1には弟ゲオルクと合作による彫金のレリーフが出品されていました。また、弟エルンストの娘を描いた《ヘレーネ・クリムトの肖像》は、額縁に梅花の枝や様々な植物が描かれています。まさにジャポニスム。
◎Chapter2.修業時代と劇場装飾 男性のヌードが3点。クリムトは「女性を描く作家」として知られていますが、修業時代には男性ヌードも描いたのですね。アカデミックな画風を叩きこまれたことが分かります。《音楽の寓意のための下絵(オルガン奏者)》は、顔が描かれていないのが面白かったです。下絵なので、省略したのでしょう。《紫色のスカーフの婦人》には「古い写真を使って制作したのだろう」という解説が付いていました。
◎Chapter3.私生活 何といっても「14人の子どもがいた」ことにびっくり。また、弟エルンストの妻の姉エミーリエ・フレーゲとの関係について、解説には「プラトニックなものとされてきたが、近年発見された手紙から二人がある時期深い関係にあったことが推測されている」と書いてありました。
◎Chapter4.ウィーンと日本1900 東洋美術に関するクリムトの蔵書が出品されています。『日本の春画三十六選 菱川師宣、鈴木晴信、喜多川歌麿』の展示では、喜多川歌麿「歌まくら」のうち第8図、第10図のモノクローム図版も見ることができました。クリムトは、この絵から「肝心なところが見えそうで見えない」という描写を学んだのでしょうか。《赤子(ゆりかご)》には「遊女や武士が色鮮やかな着物姿で生き生きと描かれた歌川豊国の影響(略)」という解説が付いていました。
◎Chapter5.ウィーン分離派 この章の見どころは《ユディトⅠ》《ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実》と《ベートーヴェン・フリーズ(原寸大複製)》。6月9日放送のNHK・Eテレ「日曜美術館」と6月22日放送のテレビ愛知「美の巨人たち」の両番組とも「《ユディトⅠ》のモデルはアデーレ・ブロッホ=バウアー」と解説していました。また、この章に出品されていたクリムトの赤いスケッチブックには《ヌーダ・ヴェリタス》のデッサンが描かれていました。
◎Chapter6.風景画 東京で本展を見た協力会会員のMさんが「クリムトの風景画が素晴らしかった」と絶賛していたのでワクワクしながら見ましたが、その通りでした。壁一面にクリムトの風景画を2点だけという、特別待遇の展示です。 《アッター湖畔のカンマー城Ⅲ》の解説には「おそらく望遠鏡を用いて描かれた(略)」と書いてありました。写真で言うところの「望遠レンズの圧縮効果」を利用して、奥行きを縮めた作品ですね。この作品、「奪われたクリムト」(エリザベート・ザントマン著、永井潤子・浜田和子訳、梨の木舎発行)によれば、1910年にアデーレ・ブロッホ=バウアーが夫フェルディナントと共同で購入。アデーレの死後、1936年に夫がオーストリア国立絵画館に寄贈。その後、ナチスが強奪した《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ》をオーストリア国立絵画館が引き取る見返りとして、クリムトとマリア・ウチッカーとの間の子どもで映画監督のグスタフ・ウチッカーに「グスタフの死後はオーストリア国立絵画館に寄贈する」という条件で渡った、とのことです。
◎Chapter7.肖像画 《オイゲニア・プリマフェージ》と、その習作が並んでいます。習作の段階では、少し右を向いていたのですね。《白い服の女》は未完成ですが、「このままでもすばらしい」と思える作品でした。
◎Chapter8.生命の円環 生後わずか81日で急死した息子を描いた《亡き息子オットー・ツィンマーマンの肖像》には胸が痛みました。見どころは《女の三世代》ですが、デッサンも見逃せません。ただ、《横たわる恋人たち》《右を向く恋人たち》は上の方に展示されているため、何が描いてあるか、よくわかりませんでした。(図録を買って納得しましたが……)
◆クリムトが生きた時代(「ハプスブルク帝国」岩﨑周一著 講談社現代新書2442 から抜粋) P.314~316
(略)1873年に来墺した岩倉使節団の記録書『米欧回覧実記』には、「人民ノ品位ニヨリテ、接遇ノ異ナルコト、我明治以来ノ光景ニ異ナラズ」と記されている。また、世紀転換期にオーストリア=ハンガリー駐在大使を務めた牧野伸顕(大久保利通の次男。内相、宮相、外相などを歴任)の叙述によれば、「すべてが宮廷中心に出来ているウィーンの社会は、フランス革命後に取り残された欧州の貴族階級によって維持され、従ってウィーンという都会には、或る特殊な雰囲気があった」。
こうした大貴族に加え、中小の貴族と有産市民が工業化の進展によって台頭したことは、消費文化の進展を促した(「ミナ貴族豪家ノ奢侈ヲ競フヲ以テ、製作ミナ精微ヲ極メタル」〈『米欧回覧実記』〉。成功した有産市民―クリムトによる夫人アデーレの肖像画が有名な製糖業者フェルディナント・ブロッホ=バウアー、哲学者ルートヴィヒとピアニストのパウルを息子にもった鉄鋼業者カール・ヴィトゲンシュタインなどの実業家たち―は、貴族の行動・生活様式(召使の雇用、芸術活動の後援、フランス語の習得など)を模倣して、「顕示的消費」(ソーステイン・ヴェブレン)に走った(カフカや詩人トラークルはこのような事情から、少年期にフランス語を学ばされている。)また彼らは、ホーフマンスタールとリヒャルト・シュトラウスが(時代設定こそマリア・テレジア期だが)楽劇『ばらの騎士』で活写したように、差異化を意識し打算を絡めながらも貴族と交流し、結びつきを強めた。
富裕層の要求に応えるべく、主要都市には貴族の邸宅を模して、ネオ・ルネサンスもしくはネオ・バロック様式の瀟洒な高級アパートメントが多数建てられた。ウィーンのリングシュトラーセ沿いに林立するアパートメント群はその好例で、ここに居住した富裕層は「リングシュトラーセ男爵」と呼ばれた。まさしくこの呼び名が示す通り、このアパート群は、「ブルジョワと貴族の和解」(カール・ショースキー)の象徴であった。(抜粋、終わり) クリムトの活躍は、ブルジョワの台頭を背景にしていたのですね。
◆最後に
本展は、この夏お勧めの展覧会です。 ただし、当日、2時間ほど展示室の中にいたら体が冷えて困りました。外気温が高いので、どうしても薄着になります。その上に汗をかいて美術館に入ると、冷気に襲われること確実です。羽織るものを用意するなど、冷房対策をお忘れなく。また、土日に来場する方は、長い行列ができる可能性もあるので熱中症対策も必要です。 Ron.

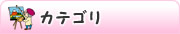
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.