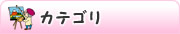名古屋市美術館(以下「美術館」)で開催中の「ボテロ展 ふくよかな魔法」(以下「本展」)の協力会向け解説会に参加しました。参加者は49名、猛暑とコロナ禍での開催としては、予想以上に多い人数です。講師は、本展担当学芸員の久保田舞美さん(以下「久保田さん」)。解説会では初めてお目にかかる学芸員さんです。2階講堂で本展の解説を聞いた後、自由観覧・自由解散となりました。
◆久保田さんの解説の要点 (16:03~45)
以下、久保田さんの解説の要点をかいつまんで記します。
〇ボテロの略歴
1932年、南米コロンビアのメデジン生まれ。現在90歳で、現役の世界的作家。ゲルハルト・リヒターと同じ年の生まれ。「現在も現役の世界的作家」という点も共通。絵画だけでなく、彫刻も制作。1949年、ピカソの評論を地元の新聞に投稿し、高校から退学処分を受ける(17歳)。1956年、マンドリンの穴を小さく描いたら、マンドリンのボリューム感が増すことを発見(24歳)。1959年、第5回サンパウロ・ビエンナーレに、コロンビア代表として《12歳のモナリザ》を出品(27歳)。1961年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)が《12歳のモナリザ》(1959)を購入(29歳)。1963年、メトロポリタン美術館がレオナルドダヴィンチ《モナリザ》を展示しているときに、MoMAが《12歳のモナリザ》を展示して、注目を集める(31歳)。
〇本展について
日本では26年ぶりの大規模展。愛知県では初めての展覧会。ボテロ本人が監修した70点の絵画を出品(彫刻はない)。展示作品のほとんどが、日本初公開。なかでも《モナリザの横顔》(2020)は、世界初公開。
〇出品作品について
出品作品に関する久保田さんの解説については、次の「自由観覧」の中で触れます。
◆自由観覧(16:45~18:00)
〇第1章 初期作品
《泣く女》(1949)は、17歳の時の作品。久保田さんによれば「ピカソの『青の時代』の影響を受けているほか、オロスコなどのメキシコ・ルネサンスの壁画の影響も受けている」とのことです。ボテロは、17歳の時から「ボリュームのある人物」を描いていますが、この時代は手や足など「体の末端が肥大」しているように見えます。また、久保田さんの解説によれば《バリェーカスの少年(ベラスケスにならって)》(1959)は「《12歳のモナリザ》に似ている作品」です。《庭で迷う少女》(1959)も《馬に乗る少女》(1961)も、この時代の作品は「ふくよかな人物」というよりも「二頭身の人物」を描いているように見えます。
〇第2章 静物
《楽器》(1998)に描かれているギターは穴がとても小さく「ボテロが1956年に描いたマンドリンも、こんな姿をしていたのかな?」と思わせる作品でした。ピンク色の布(ふとん?)の質感描写も素晴らしいと思います。《洋梨》(1976)について、久保田さんは「伝統的な静物画のジャンル=ヴェニタス(人生のむなしさの寓意)を踏まえて、腐りかけの果物を描いたもの。果物をかじった跡や、穴、果物を食べている虫を描いているのは、そのため」という趣旨の解説をされました。「虫は目も描かれていて、かわいい」と、付け加えています。「腐りかけ」というなら「萎れて崩れかけた果物を描く」という手もあると思いますが、さすがはボテロ。腐りかけの果物であっても、みずみずしさにあふれています。一方、果物のヘタだけでなく、誰かが齧った跡、虫、どれをとっても小さいので、洋梨のボリューム感は半端ないものでした。
解説の最後に、参加者からの「ボテロにとって、青はテーマカラーですか?」という質問に対し、久保田さんは「青、赤、緑のバランスを取っている。大小のバランスも取っている。青が特別な色という訳ではない」と回答していましたが、《黄色の花(3点組)》《青の花(3点組)》《赤の花(3点組)》(いずれも2006)の三点は、久保田さんの回答のとおり、色のバランスを取った作品でした。特に《青の花》《赤の花》は、花と花瓶の色が補色関係になっており、色の対比とバランスを考えた作品だと思います。
〇第3章 信仰の世界
《キリスト》(2000)を見て、特定の年代の参加者は「俺たちひょうきん族の神様にそっくり」と言っていました。若い人には何を言っているのか分からないと思いますが、とにかく似ています。《コロンビアの聖母》(1992)について解説の最後に、参加者から「幼いキリストと思われる子どもが現代風の服を着ているのは、何故ですか?聖母がつまんでいるのは果物ですか?」という質問がありました。久保田さんの答えは「ボテロに聞けば、ピンクが欲しかったから、と答えるかもしれません。聖母がつまんでいるのは果物です。子どもがつまんでいる小さなものは、コロンビアの国旗。ボテロが、この作品を描いたのは1992年当時のコロンビアの暴力的な環境にあるのでは、とも思いますが、答えは不明です」というものでした。1992年といえば、1984年から続いた、麻薬組織メデジン・カルテルとコロンビア政府との「麻薬戦争」が終結した年です(Wikipediaによる)。久保田さんによれば、《守護天使》(2015)は「ボテロの自画像」です。

〇第4-1章 ラテンアメリカの世界
最初に展示されているのが《バルコニーから落ちる女》(1994)。何が起きたのか、よくわかりませんが、説明書きには「陰謀の犠牲者か?」と書かれています。《ピクニック》(2001)に説明書きはありませんが、「芸術新潮」2021年12月号は「草原でくつろぐ男女は、マネの《草上の昼食》が元ネタ」と書いています。言われてみれば、そんな雰囲気が漂っています。元ネタそのままではなく、一度自分の中に取り込んでから「ボテロ流」に再構成した作品ですね。ボテロの作風には、揺らぎがありません。《通り》(2000)に違和感を覚えたので説明書きを見ると「現実にはあり得ない空間。(略)絵画とは現実を表したものではなく、個人的な現実を独自の視点と体験をもとに創り上げたもの」と書かれていました。
〇第4-2章 ドローイングと水彩
4-2章からは2階に展示。キャンバスに青鉛筆で描き、水彩絵の具で彩色した作品が並んでいます。いずれも、2019年に制作したもの。思わず「うまい」と、声を出してしまいました。描かれているのは、どれも「ふくよかな」人物ですが、油絵と違って「凛々(りり)しく」、違和感がありません。とはいえ、作風そのものは、まったく変わっていませんでした。
〇第5章 サーカス
「サーカス」で一つの章を構成するのですから、サーカスは、ボテロにとって「欠かせないもの」だったのでしょうね。どの作品にも、補色関係である緑と赤の対比が使われていました。「現実にはあり得ない遠近感」も、楽しめます。
〇第6章 変容する名画
名画がどのようにデフォルメされたか分かるように、元ネタとボテロの作品を並べて展示しています。なかでも、久保田さんが力を入れて解説したのは《ピエロ・デラ・フランチェスカにならって(2枚組)》(1998)でした。キーワードは「この作品には、フランチェスカに対する尊敬があらわれている。陰影を強くつけることなく、線と色彩でボリューム感を出している。フランチャスカを思わせるのは、無表情ではなく、口角を挙げて少し微笑んでいること。ボテロの様式で描いた、気分の上がる作品」等です。展示室で見ると、とても大きな作品でした。画面の上下を縮めて「ふくよか」な感じを強調していますが、他の作品に比べるとデフォルメの程度は小さく感じます。この作品で見入ったのは、服や帽子、髪飾りなどの質感描写です。イタリアで基礎を学んだだけあって、久保田さんの解説どおり「線と色彩でボリューム感」を出していました。質感も出ています。ボテロなら、元ネタそっくりに描くことも出来るでしょうが、それでは「模写」であって彼の「作品」にはならないので、デフォルメした作品を制作したのでしょう。絵の向きも、元ネタの逆です。他に目を引かれた作品が《フォルナリーナ(ラファエロにならって)》(2008)でした。ボテロの描く人物の多くは無表情ですが、このフォルナリーナの眼差しや唇は、妙に色っぽいのです。《モナリザの横顔》(2020)にも表情があります。このことを久保田さんに質問したところ、「微笑や眼差しは、作品を特徴づけるもので、不可欠な要素。なので、デフォルメしても、残したのではないか」という趣旨の回答をいただきました。上記以外の作品も「元ネタそのまま」ではなく、人物の向きや、服装などを変化させています。それを発見するのも、鑑賞の醍醐味だと思いました。
◆ボテロとゲルハルト・リヒターは、共通点があるものの、対照的な作家
ボテロもゲルハルト・リヒターも1932年生れで、世界的な作家、日本で大規模な巡回展が開催されている、という共通点があるものの、素人ながら対照的な作家だと思います。ボテロは20歳の時に描いた作品が第9回コロンビア・サロンで二等賞を獲得。その賞金でヨーロッパに渡り、プラド美術館でゴヤやベラスケスを模写。その後パリに移り、ルーブル美術館で巨匠の作品を模写。更にフィレンツェに移り、サン・マルコ・アカデミーに入学。フレスコ画の技法を学び、フィレンツェ大学美術学科でロベルト・ロンギの講義を受けています。抽象絵画が主流の時、古典絵画をデフォルメするという作風を確立してからは、作風を変えていません。一方、リヒターは東ドイツで描いていた「社会主義リアリズムの壁画」に疑問を持ち、西ドイツに出国。デュッセルドルフで抽象絵画の洪水に出会い、模索の後、フォト・ペインティングで評価されます。その後、カラーチャートやアブストラクト・ペインディングなど、具象と抽象の間で作風は変遷しています。「どちらが良いか」というのではなく、今年は対照的な二人の作家の展覧会を続けて鑑賞することができる、又とない機会だということです。
◆最後に
正直に言うと、あまり期待せずに来たのですが、良い意味で裏切られました。いずれの作品も「ふざけて、ふくよかな人物を描いたのではなく、元になった名画に敬意を表して、まじめに描いたもの」でした。大きな作品が多く、見応えがあります。解説会にも予想以上の数の参加者がありました。お薦めですよ。
Ron