『ある画家の数奇な運命』は2018年制作のドイツ映画、ドイツを代表する現代美術家ゲルハルト・リヒター(以下「リヒター」)をモデルにした作品です。協力会のS氏から「リヒターの映画が10月2日から上映される」というメールを受けた後、9月25日発売の『芸術新潮』10月号「art NEWS」が取り上げ、10月1日発売の『週刊文春』10月8日号でも「Cinema Chart」「Close Up」と、二つの記事で取り上げていたので、矢も楯もたまらず伏見ミリオン座に出かけました。伏見ミリオン座では手指の消毒とマスク着用が求められたものの、入場制限はありませんでした。映画の上映前に、室内の換気が徹底されていることをアピールする動画が流され、テレビでお馴染みの愛知医科大学病院・三鴨医師も太鼓判を押していたので、新型コロナ感染予防策については安心しました。
序盤=話の中心はエリザベト叔母さん
映画の上映時間は189分。3時間を超す大作です。映画の舞台は大きく三つに分かれ、第二次世界大戦前と戦中のドイツが序盤の舞台です。リヒターの叔母(母親の妹)エリザベトを中心にストーリーが展開します。始まりは1937年、「頽廃美術展」のドレスデン会場(史実では1933年開催)。作品を解説する人物が口汚く罵るモンドリアンやカンディンスキーの抽象画を見ながら、エリザベトが5歳のクルト(モデルはリヒター)に「わたしはこの作品が好き」(日本語字幕の映画なので、話しているのはドイツ語)とささやく場面が印象的でした。
エリザベトが統合失調症と診断され、数人の病院職員の手で救急車に押し込まれるとき、クルトに向って「目をそらさないで」と叫ぶ場面は、見ていて辛かったですね。当時のドイツでは、優生思想(遺伝的に劣った人間を社会から排除すべきという考え方)に基づき、障害者を「青の-=断種手術」と「赤の+=無価値な命」とに区分することを決定。彼女は病院のゼーバント院長(産婦人科医)に何度も「助けて」と懇願しましたが、「赤の+」との鑑定を受けます。直ちにグロスシュヴァイトニッツの施設に送られ、その後、多くの精神障害者・知的障害者と一緒にガス室に送られます。大空襲でドレスデンの街が真っ赤になり、多くの人命が失われ、美しい街並みがことごとく破壊された後、1945年5月8日にソ連軍がやって来て戦争関係者を取り調べる場面で序盤は終わります。
中盤=義父の圧力で重苦しい展開
第二次大戦終結後の東ドイツが中盤の舞台です。1951年、クルトは工場で看板の文字を書く仕事をしていますが、その才能が認められ、ドレスデンの美術学校に入学することができます。美術学校でクルトは被服科の女学生エリザベト(以下「エリー」)と知り合い、二人は恋に落ちます。クルトがエリーの家に行くと、そこは3階建ての豪邸。何と、エリーの父親は叔母のエリザベトを「赤の+」と鑑定したゼーバント院長でした。彼はナチ政権による障害者の大量殺人に加担した疑いでソ連軍の取り調べを受けましたが、ある事情で釈放され、病院長に復職していたのです。一方、クルトの父親はナチス党員だったことで教師の職を失い、病院の清掃夫をしていましたが、自殺してしまいます。(リヒターの父は自殺していません)1956年、ドレスデンの美術学校の卒業制作が評価されてクルトは壁画制作をまかされますが、社会主義リアリズムの絵画に疑問を感じるようにもなっています。
その後、ナチ政権における障害者大量殺人の関係者を捜索するソ連軍の動きが迫っていることを知ったゼーバント院長は、捜索を逃れるため西ドイツに渡り、西ドイツで職を得ます。クルトとエリーも1961年3月31日に、西ベルリンを経由して、西ドイツに渡ります。中盤はここまで。なお、ベルリンの壁ができたのは1961年8月13日。映画の終盤に、クルトが壁の建設を知る場面があります。
終盤(前半)=苦闘するクルト
西ドイツが終盤の舞台です。先に西ドイツに渡った仲間は、クルトに「絵画を続けるのなら、前衛的なデュッセルドルフはやめておけ」と忠告しますが、クルトは敢えてデュッセルドルフの芸術アカデミーへの入学を選択。デュッセルドルフの芸術アカデミーには、木製の机や椅子に釘を打ち付けて作品を制作するハリー、角材を組み合わせたオブジェにジャガイモを貼り付けるアーレント、壁紙のような作品を制作し、商売上手なアドリアン・シンメルなど個性的な学生が揃っていました(いずれも、モデルの作家あり)。極めつけは、いつも帽子を被り、フェルトと脂で作品を制作するフェルテン教授(モデルはヨーゼフ・ボイス)。クルトは、彼の指導の下で学びます。
前半の最後近くに、フェルテン教授がクルトに「作品を見せてほしい」という場面があります。クルトの作品を見たフェルテン教授は、「タタール人は頭の傷口に脂を塗り、体をフェルトで包んだ。1年間、彼らに世話をしてもらった後、米軍の捕虜となった。それ以来、脂とフェルトは私に染みついている」と、第二次世界大戦中に乗っていた爆撃機が墜落して、タタール人に助けられた話(「ボイスによるフィクション」とWikipediaが書いてるエピソード)をします。そして、クルトに「君は誰だ。何者なのだ。これは君じゃない」と言って、部屋を去ります。教授が去った後、クルトは、それまでの作品をすべて燃やし、白いキャンバスに向いますが、何も描けません。
その後、義父のゼーバントはクルトに「30歳にもなって、まだ学生か」と言い、金銭の支援を申し出ますが、クルトは拒絶。それではと、義父は病院清掃作業のパートを斡旋。クルトは一日3時間、掃除夫の仕事を始めます。
終盤(後半)=成功に向けてまっしぐら
ある日、義父はクルトを喫茶店に呼び出し、パスポートの申請に必要な資料を役所に届けるよう依頼。そこに、新聞売りが「安楽死の首謀者逮捕」と言って、障害者大量殺人の首謀者ブルクハルト・クロル(史実では、ヴェルナー・ハイデ)の写真が1面に載った新聞を売りに来ます。新聞をちらっと見た義父は、あわてて退席。クルトは店から出るとき、見ず知らずの客から、逮捕記事が載った新聞を譲り受けます。
クルトはアトリエで、新聞に載った首謀者の写真に縦・横の線を等間隔に引き、キャンバスにも同様に縦・横の線を等間隔に引いて、縦横の線を基準にして写真をキャンバスに模写。首謀者の写真の模写が完成すると、次にエリザベトとクルトが一緒に写っている写真を模写。この模写が完成すると、義父のパスポート写真を模写に投影。その後、エリザベトとクルトが一緒に写っている写真の模写の上から刷毛で白い絵の具を塗り重ねて像をボカします。そう、「フォトペインティング」の完成です。クルトは更に、エリザベトと義父、首謀者の写真を重ねて、模写を制作。ある日、クルトのアトリエに入ってきた義父は、エリザベトと義父、首謀者の三人が描かれた作品を見て、ひどく取り乱します。隣のアトリエにいたハリーはびっくりして、義父が取り乱した理由を聞きますが、クルトにもわかりません。クルトは、それとは知らずに、義父を告発する作品を描いていたのです。
クルトは自分の進むべき道を見出しただけでなく、妻の妊娠も知ります。クルトは、アカデミーの階段を下りてくる全裸のエリーをローライの二眼レフで撮影して、フォトペインティングの作品を制作します。
映画の中盤で、自殺した父親と統合失調症の叔母を持つクルトの遺伝子を受け継ぐ孫の誕生を嫌悪した義父は、嘘を言って、自宅でエリーに人工妊娠中絶を施術しています。この手術の影響でエリーは妊娠しにくい体になっていたため、「妊娠できたこと」はクルトとエリーにとって、この上ない喜びでした。
1966年、アドリアン・シンメルはクルトのために個展を企画。テレビ局の記者が、《母と子》(エリザベトとクルトが一緒に写っている写真を模写)の前で、「無作為に選ばれた写真を模写しているが、何故か力がある。死んだと言われた絵画は、『作者なき作品』という手法で復活した」と、個展を紹介。個展は大成功でした。個展会場を後にしたクルトは路線バスの車庫を見つけ、運転手にお願いして複数のバスのクラクションを一斉に鳴らすという、エリザベトが好んだ悪戯をしました。クルトはバスのクラクションを全身で受けとめ、個展の成功に酔いしれます。クルトの成功は、今は亡きエリザベトが導いたものだったのです。
映画の中のフィクションと事実
週刊文春の「Close Up」には「リヒターは映画化にあたって、登場人物の名前を変えること、何が事実かを明かさないことを条件に出した」と書いてあります。現在、NHKで放送中の「エール」も、作曲家・古関裕而をモデルにしていますが、主人公の名前は古山裕一。また、そのストーリーは事実とフィクションが入り混じったものです。この映画も「エール」と同じですね。「パラレルワールドのリヒター伝」と割り切って鑑賞しました。
映画に登場した作品について
『芸術新潮』の記事によれば「映画に出てくる作品はリヒターの実作をもとに、彼のアシスタントが制作した」とのことです。私は、映画に出てくる作品のうち《母と子》のモデルを、2014年、名古屋市美術館に巡回した「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展」という実に長い題名の展覧会で見たことがあります。それは《叔母マリアンネ》(1965)という、赤ん坊を抱く、あどけない少女の像でした。説明を読んでも、何で描いたのか良く理解できなかったのですが、この映画で、作品が制作された背景を窺うことができました。また、全裸のエリーを描いた作品のモデルは《エマ 階段を降りる裸婦》。ネットを検索すれば見ることができます。
映画の題名について
ドイツ語の原題は、“WERK OHNE AUTOR”(作者なき作品)で、リヒターの制作手法を表わしたものです。英語の題名は、”Never Look Away”(目をそらさない)。映画の中でエリザベト叔母が叫んだ言葉によるものです。また、週刊文春「Close Up」は、リヒターは「何を質問したとしても、この人は賢いとか愚かだとか考えずに答えてくれるんです。まさに ”Never Look Away” を体現している人」と書かれています。
『ある画家の数奇な運命』という日本語の題名は映画の内容を説明していますが、この作品はクルト個人の数奇な体験だけではなく、ナチス政権化のドイツ、東西分裂後の東ドイツ、前衛芸術の運動が爆発していたデュッセルドルフなど、激動の時代も描いている広くて深い内容のものでした。
最後に
来年、フェルテン教授のモデルになったヨーゼフ・ボイスの展覧会「ボイス+パレルモ」が豊田市美術館(ヨーゼフ・ボイスの作品を所蔵)で開催されます。「開催時期は調整中」とのことですが、楽しみですね。
Ron.

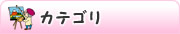
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.