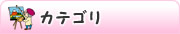名古屋市美術館で開催中の「辰野登恵子 ON PARERS」(以下「本展」)の協力会ギャラリートークに参加しました。担当は清家三智学芸員(以下「清家さん」)。参加者は52人と多かったのですが、ポータブル拡声装置を使えば離れた参加者にも清家さんの声が届くので、全員が一緒に動きました。以下は、清家さんによるギャラリートークの要約筆記で、(注)は私の補足です。
なお、ギャラリートークに先立って、2階講堂で辰野登恵子(以下「辰野」)の略歴が紹介されました。

50名をこえた参加者
◆2階講堂にて
辰野は1950年、長野県岡谷市生まれ。3人姉弟の第2子で姉は2歳上、弟は5歳下です。辰野が子供の頃、通っていたお絵描き塾の先生が「風景を自由に描いて」と課題を出したところ、マティス風に真っ赤に塗った絵を描いて提出したというエピソードがあります。辰野は、幼い時から色づかいに「こだわり」のある人でした。
辰野は大学進学のため、高校2年生の時から週末や夏休みなどを利用して、美術系予備校の「すいどーばた美術学院」(東京都豊島区西池袋)に岡谷から通い始めました。また、高校時代は学校が開く時刻に登校して美術室で絵の勉強。授業終了後も学校が閉まる時刻まで美術室に居たそうです。努力の甲斐あって、辰野は東京芸術大学(以下「芸大」)の油絵科に現役合格します。当時の合格者は50名、女子は10名、うち現役合格は4名でした。
芸大入学後、1969年には学園紛争のため大学の授業がなくなります。そんな状況でも辰野は芸大に通い続け、版画教室で当時の教官の駒井哲郎、中林忠良の指導を受けています。油絵科の学生でしたが制作したのは写真製版によるシルクスクリーンの作品です。辰野はアンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインなどのポップアートの影響を受け、映像を作品に生かそうとしていました。「映像を作品に生かす」には、油絵でカンバスに描くよりもシルクスクリーンで紙に刷る方が合っていたのです。
本展は、辰野の回顧展としては初めての展覧会です。2階にⅠからⅣ、1階にⅤ・Ⅵ・Ⅷ、地下1階にⅦを展示しています。それでは、2階の展示室に移動してください。
◆Ⅰ
Ⅰは主に大学・大学院6年間の作品で、ウォーホルやリキテンスタインの影響が見られます。大学・大学院時代の辰野は「絵の中に映像を取り込む」作品を制作しています。作品No.2《Self portrait》は自分の写真を写真製版してシルクスクリーンでカンバスに印刷したもので、作品No.3《無題》キャベツを写真製版して、いくつも印刷したものです。
シルクスクリーンは同じイメージを何度も使うことができるだけではなく、刷り方を変えることによって「100パーセン完璧なコピー」ではなくなり少しずつ異なったものができるところに、辰野は関心をもちました。
当時の辰野は芸大同級生の柴田敏雄さん、鎌谷伸一さんと3人で「コスモス・ファクトリー」という制作集団をつくり、写真は3人で共用、ステンシルも3人で共用して作品制作を行いました。作品No.10-1~10-4《無題》は大学院修了制作で、9点制作したうちの4点を展示しています。作品のモデルはマイケル・ダグラスの父親のカーク・ダグラスで、イエナ書店で売っていた洋物の雑誌に掲載されていた映画「チャンピオン」の写真をコピーしたものです。作品No.7《9つの長方形》は、その後の辰野作品の原点で「同じ形が、少しずつ印刷を変えながら反復する」というところに特色があります。
◆Ⅱ
本展に学芸員が書いた解説パネルの掲示はありません。解説パネルの代わりに、作家本人のことばを「切り文字」で壁に貼りました。Ⅱでは、辰野の言葉は「ノートの横線や、原稿用紙のます目や、網点や、そういう整然と並んでいるものを、じっと見ているのが大好きで、そういう不毛なところに、もし、何かを一点落としたら、全然違ったものに変身するでしょ。点ひとつで、新しい空間が出現する。」というものです。「整然とならんでいるもの」を「不毛なところ」というのは辰野独特の表現ですが、「整然とならんでいるもの」が作家の関わり方によって微妙な差が生じ立体感や奥行きが生まれるのが楽しい、という気持ちがよくわかります。
Ⅱで展示している作品は、いずれも辰野の実験です。実験する中で、辰野はグリッド(格子)の規則性を破るのを楽しんでいます。男性の皆さんにはわかりにくいかもしれませんが、辰野は「規則性を破るのを楽しさ」を「ストッキングが伝線する瞬間が好き」と表現しています。「伝線する瞬間が好き」とは規則性が揺らぐ瞬間が好きということであり、グリッドなどに対して、その規則性を破るような関わり方がしたいということです。
Ⅱに展示しているのはすべてシルクスクリーンの作品で、規則正しい反復に破綻が生じて出現した「新しい空間」を表現しています。
◆Ⅲ
Ⅲで展示しているのは「地下鉄のホームの壁のタイル」など、現実世界にある格子状のものから、タイルの厚みや奥行きなどの現実にある歪みを読み取ってデザインし、それに濃淡を加えて描いた作品です。それは「現実そっくり」に表現するのではなく、自分の感覚を加え、絵画という空間の中で何ができるかデフォルメする実験でした。絵画空間という架空の世界、イリュージョンを描いています。
Ⅲでは罫線が登場します。そして、「罫線」という一つのものを、①罫線そのものと②罫線で囲まれた領域という二つの視点で描いています。コクヨの罫紙をコピーして、シルクスクリーンで色を重ねました。塗り重ねる都度、版に目止め剤を塗って色を変えた作品もあります。
Ⅲの終わりに油彩画が登場します。作品No.59《WORK-78-P-14》はミニマリズムの絵画です。
(注:Ⅱは抽象的な図形の規則性を破った時に生ずる新しい空間を描いた作品であるのに対し、Ⅲでは壁のタイルや罫紙など現実世界にある要素が表現に作品に加わってきます、装飾的要素を最小限に切り詰めたものになっている、ということでしょうか)
◆Ⅳ
辰野の言葉は「切り文字」です。シートに文字の形に切り込みを入れて壁に貼り付け、その後、文字以外の部分を剥がして作りました。パネルの掲示よりも手間がかかりますが「作品以外のものに物質感を持たせたくない」ので、パネルでなく「切り文字」を貼ることにしました。
Ⅲの最後の油彩の作品No.59《WORK-78-P-14》は名古屋で発表されたものです。辰野は1978年に名古屋の「ギャラリーたかぎ」で油彩の個展を開いています。この作品では、それまでの作品にあった規則性を離れ、フリーハンドでの絵画制作にチャレンジしています。
Ⅲまではグリッドや罫線など前提になる形があったのですが、Ⅳで油彩に戻ると表現の自由度が増して、色づかいや画面構成に気を配るようになります。また、油彩とシルクスクリーン、カンバスと紙、という違いを自分の手で確かめながら試行錯誤をしています。したがって「一つ一つ作品それぞれに意味がある」というよりも、すべて実験結果です。なお、辰野は「色づかいには自信がある」と言っています。一方で「デッサンは苦手」とも言っていますが。
作品No.68《WORK80-P-22》と作品No.69《無題》には、次に続くⅤの作品群の片鱗が見られます。このように作風が変わるきっかけに、辰野の結婚があったという見方もあります。辰野は理知的な性格ですが、結婚によって夫の「感性を素直に表現する」という考え方に影響を受けたのではないかというのです。一方で「自分がやりたいから作風が変わったのではないか」という見方もあります。
それでは1階に移動しましょう。

◆Ⅴ
Ⅴの展示空間は中央に柱があります。展示空間の真ん中に柱を置くような配置は避けるのが普通ですが、1階は大きい作品が多いので広い空間を確保するため、あえて柱を残しています。
辰野はⅤで作品の画面構成に試行錯誤をしています。Ⅳの作品のように色を上から下に垂らすだけなら、描く物体の形や画面構成を意識しなくてもよいのですが、「自由に描く」となったら「画面へのおさまりやすさ」も考える必要があります。辰野はⅤで、長方形の画面の中に菱(◇)型の物体を描いたり、右上から左下に対角線を描くなどの試行錯誤を繰り返しました。
画材も、いろいろと試しています。水彩や鉛筆はサラサラ描けますが色は弱い、油彩だと色は強いのですが絵の具が乾くのに時間がかかります。銅版画だとエッチングやドライポイントならシャープな線が描け、アクアチントなら色面を作ることができます。パステルだと物体や背景を「ぼかす」ことができます。
◆Ⅵ
Ⅵに掲げた辰野の言葉に「イメージは見えている世界からピックアップされてくるものもあれば、心の闇から生まれてくるものもあります。」という一節があります。この「見えている世界からピックアップされてくるもの」のひとつが「原稿用紙」です。Ⅵでは、①原稿用紙の枡目の枠と②枡目で囲まれた領域、という2種類のドローイングが登場します。チラシやポスターで使った画像の作品No.109《Oct-20-95》は原稿用紙の枠をピックアップした作品で、国立国際美術館コレクションの作品No.124《March-3-98》は、囲まれた領域をピックアップした作品です。
また、地と図形の関係、つまり「地の処理を変えることで、どのように図を目立たせることができるか」も試しています。たとえば、作品No.107《無題》では図の内部を黒くすることで図が浮き上がってきます。作品を見くらべてください。
Ⅵには「ザ 辰野登恵子」というべき作品が並んでいます。なかでも、大型の作品は上部の解放感が必要なので吹き抜けに集めました。市美所蔵の特別出品《WORK86-P-12》も大型で、しかも左右の空間が必要だったため、結果的に通路の正面という一番目立つところに展示することになってしまいました。

清家学芸員、ちょっと風邪気味でした
◆Ⅷ
辰野は2011年と2012年にフランスに渡り、パリの版画工房イデム(IDEM)でリトグラフを制作しています。イデムは石灰石の版を用いたフランスの伝統的な技法でリトグラフを制作する工房です。伝統的な技法による版画制作は辰野にとって初めての体験でした。制作を始めると、今までの版画制作の経験が使えないということが分かり、これまでの自分のやり方を一度捨てて、一から描いたイメージで版画を制作しました。
ご覧いただくとわかるように、Ⅷには今までとは違うイメージの作品が並びます。なかでも、作品No.215《望まれる領域》は最晩年の作品で、さらなる発展を考えていたことが感じられます。メインの赤いモチーフに青やピンクの背景を組み合わせた作品ですが、左下に異質なものが描かれています。
それでは、地下1階に移動します。
◆Ⅶ
Ⅶは信濃毎日新聞に連載された辻井喬(堤清二)のエッセイの挿絵として制作した作品です。紙面コピーをファイリングした資料も用意しています。作品は辰野の故郷の岡谷市で両親の介護をしているときに制作したものです。ご覧いただいているように、月やミモザの葉、連なる山など身の回りの景色や物から得たイメージを描いています。
(注:Ⅶで展示されている作品は新聞連載の挿絵ということもあってか、親しみやすいものでした。参加者からは「この作品なら、部屋に飾りたい」とか「Ⅶの画集が出たら、絶対買うのに」などの声がありました)
◆Q&A(地下1階・常設展示室3にて)
Q1 Ⅰの作品No.4《無題》に描かれているスリッパの中に、スリッパを剥がしたような跡があるのですが、作家はわざと剥がしたのですか。
A1 その通りです。最初はスリッパをコラージュしていたのですが、それを剥がしています。
Q2 Ⅶに展示してある作家の写真は学生時代に撮影されたものですか。
A2 その通りです。大学院の研究室で撮影されたものです。マギーブイヨンの缶が写りこんでいますね。雑然とした様子は「いかにも研究室」という感じです。
(注:灰皿とタバコの吸い殻も写っていましたね)
Q3 作品のタイトルに《無題》や整理番号のようなものが多いのですが、なぜでしょうか。
A3 そのようなタイトルをつけたのは、辰野が「見方を自由にしてほしい」と考えていたからです。「見る人がいろいろ違ったことを考えてくれるのが一番うれしい」ということですね。
Q4 展覧会のチラシやポスターの画像などは、巡回する美術館で統一しているのですか。
A4 美術館ごとに違う画像を使っています。市美では、辰野作品のイメージがよくわかるⅥの作品No.109《Oct-20-95》を使っています。油彩の作品を推す声もありましたが「オン ペーパーズという副題の展覧会で、カンバスの作品はまずいだろう」ということから、春らしくて明るい紙の作品を選びました。
◆最後に
ギャラリートークではレクチャーを聴くだけでなく自由に観覧する時間もあり、とても楽しく鑑賞することができて、あっという間に時間が過ぎてしました。また、Ⅶを鑑賞した後のQ&Aでは多くの質問が出され、Q4では展覧会の裏話を聴くこともできました。
参加者は皆、満足して市美を後にしました。清家さん、ありがとうございました。
Ron.

最後までていねいに興味深い解説をしていただきありがとうございました