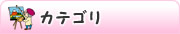◆特別展「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇」の記憶を呼び戻すために見つけた本
以前に、愛知県陶磁美術館で開催中の特別展「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇~」(以下「古伊万里展」)のブログを投稿した後、4月29日と5月8日の二回、中日新聞に古伊万里展の記事が掲載されました。この記事に触発され「古伊万里展の記憶を呼び戻したい」との思いが強くなり、近所の図書館で見つけてきたのが本書(アート・ビギナーズ・コレクション「もっと知りたい やきもの」柏木麻里 著 2020年10月25日発行 発行所 株式会社東京美術)です。書名のとおり初心者にも分かりやすい文章で、図版も豊富なので楽しく読むことができました。本書は縄文時代から昭和の陶芸までを通して説明していますが、今回は伊万里焼に焦点を絞ってみます。
◆染付
白磁にコバルト顔料で青い文様を描いた「染付」について、本書は以下のように書いています。
<14世紀に国際色豊かな中国・元朝で誕生した青花(染付の中国名)は、中東産のコバルト顔料を使い、白磁の釉下に鮮麗な青い文様を描いた。その青の輝きは世界を魅了し、東アジア、欧州、イスラム圏などへ輸出され、各地に青い絵のやきものを芽吹かせる。(略)伊万里染付磁器は、江戸時代初期の1610年代、朝鮮人陶工の手によって、九州・佐賀県有田の古唐津を焼いた窯から誕生した。(略)1640年代頃までの染付を初期伊万里と呼び、口径に比べて極端に小さい高台径など、器形に古唐津と同じ朝鮮のルーツを示しながら、その目指した様式は、桃山茶人の好んだ中国・景徳鎮窯の青花であった。17世紀中頃になると、明朝から清朝への王朝交代期の動乱から逃れて来た中国人陶工たちによって、技術も様式も一気に中国風へ舵を切る。そして磁胎、染付の技ともに洗練をきわめた17世紀末期、伊万里染付には和様の形と文様が花開いてゆく。(p.18)>
古伊万里展では「1.日本磁器の誕生、そして発展」のコーナー(以下「1.」)で、初期伊万里と中国の技術が入った後の染付を並べていました。初期伊万里は、上記のとおり小さな高台でしたが「朝鮮のルーツを示していた」ということなのですね。なお、「NHK美の壺 古伊万里 染付(2006.09.25発行)」によれば、初期伊万里の技術だと「高台を小さくしておかなければ(窯の中で焼いたとき、高温でやきものが柔らかくなると)底がずぼっと落っこちてしまう。(同書p.18)」そうです。
◆古九谷と柿右衛門
古伊万里展では、染付の次に渋めの緑、紫、黄色の色絵が展示されていました。この色絵を、本書は「古九谷」と呼び、以下のように書いています。
<古九谷と柿右衛門は姉妹である。どちらも染付に次いで登場した伊万里の色絵様式で、1640年代、中国の技術を導入して最初に誕生したのが古九谷であった。濃厚に輝く色彩で寛文小袖など、同時代のファッションに通じる意匠を描き、大名家などの国内富裕層を魅了した。柿右衛門様式は古九谷の意匠を受け継ぎながら1650年代に萌芽、17世紀末に完成する。「濁し手(にごしで)」と呼ばれる素地は鉄分による青みを取り除き、やわらかな純白を得た。そこに赤や黄、緑色などの清明な色絵具で、美しい余白をとって文様を描く。古九谷と柿右衛門の大きな違いは、その享受者にある。国内向けの古九谷に対して、柿右衛門は主に欧州の王侯貴族向けに作られた。(略)古九谷に国内の美意識が窺えるように、柿右衛門様式は、欧州貴族の好みに合わせて洗練をとげてゆく。(p.20)>
柿右衛門の展示は「1.」ではなく、「2.世界を魅了した『古伊万里』」のコーナーでした。
◆鍋島
鍋島について、本書は以下のように書いています。
<鍋島は伊万里陶磁器の中でも、将軍に献上するために作られた特別な一群である。(略)将軍家や御三家への例年献上が始まるのは17世紀半ばのこと。1690年秋には、日本磁器の最高峰といえる質に達する。元禄期に五代将軍・徳川綱吉による大名屋敷への御成(訪問)が盛んに行われ、将軍の器として、上質磁器への需要が高まったことが要因と考えられている。献上内容の大部分を大小の皿が占め、大きさも三寸、五寸、七寸、一尺と決められていた。(略)五節句など、旧暦の季節行事をモチーフとした意匠も多い。染付で文様の輪郭をとり、その中を清澄な色で染める繊細優美な色絵は、八代将軍・徳川吉宗の時代に奢侈とみなされるようになる。以後、色絵を加えない染付と青磁釉のみの装飾になるが、そこにもまた涼やかで高雅な世界が生まれる。藩窯は、幕藩体制が終焉を迎える19世紀後半まで続いた。(p.22)>
古伊万里展では「1.」の最後が鍋島で、同じデザインの皿が、色絵と染付のセットで展示されていました。色絵の皿が染付の皿に変わったのは、上記のような事情があったのですね。著者は染付を「涼やかで高雅」と表現していますが、私も展示を見て、同じような感想を持ちました。
◆金欄手
金襴手は古伊万里展のなかで一番豪華な展示でしたが、本書は以下のように書いています。
<絢爛豪華――金襴手ほどこの言葉のふさわしい日本のやきものはないだろう。柿右衛門に続いて欧州貴族を虜にしたのが、金彩を惜しみなく使った金襴手様式である。(略)重みのある色彩美は、柿右衛門様式の対極をゆく。それは、明清交代期に欧州市場を失い、17世紀末に巻き返してきた中国磁器との競争に勝利するために作られた、量産向けの新機軸であった。金襴手は欧州の城館を飾る人気商品となり、伊万里の後を追う中国の景徳鎮窯、さらに欧州各国の窯が続々と模倣するほどの影響力を誇った。金糸の入る織物を連想させる「金襴手」の名は当時から使われている。国内向けの製品もあり、好景気に沸く元禄文化の担い手となった裕福な商人たちが、贈答や宴席用に華麗な金襴手を好んだからである。欧州向けの多くが美人画や屏風など、いかにも日本風の意匠であるのに対して、国内向けの特に上質な「型物」と呼ばれる鉢には、華麗な色彩を幾何学文様の中に織り込んだ、緻密な作風が多い。18世紀中頃になると、中国との価格競争に敗れた伊万里は、ついに輸出磁器の舞台を降りる。金襴手は、輸出伊万里が最後に咲かせた大輪の花であった。(p.24)>
古伊万里展では、愛知県陶磁美術館だけの展示ですが「輸出の終焉~国内向け製品」というコーナーがありました。展示されていた「国内向け製品」の記憶は大分薄れてきましたが「緻密な作風が多い」という印象は残っています。
◆世界を駆ける伝言ゲーム
古伊万里展の第二部には、「3 城内に伝えられた西洋陶器」というコーナーがあり、オランダ、オーストリア、イギリス、デンマーク、ドイツの陶磁が展示され、古伊万里のデザインが少しずつ変化していくのを面白く見た記憶があります。この点について、本書は以下のように書いています。
<ドイツのマイセン窯、フランスのシャンティ―窯、イギリスのウースター窯などの多くの窯で、柿右衛門を写しながら磁器生産が開始され、成長してゆく。この一連の動きには、ちょうど伝言ゲームのように、柿右衛門意匠が少しずつ変化してゆくという楽しいおまけがついていた。柿右衛門の定番意匠「粟鶉文(あわうずらもん)」をみてみよう。17世紀末に輸出を再開し、欧州市場の奪還を狙う中国・景徳鎮の皿には、粟の穂の上にバッタが描き加えられ、中国草虫画(そうちゅうが)の伝統を感じさせる。そしてオランダ・デルフト窯の粟鶉文ときたらクレヨンでぐいぐい描いた童画のように、素朴な雰囲気に大変身。スタート地点の柿右衛門の、典雅な雰囲気は一体どこへ行ったのだろう。(p.70)>
(おまけ)志野と織部
愛知県陶磁美術館では常設展も見ました。2階の展示室で見た織部と鼠志野が特に印象的でしたが、志野・織部について、本書は以下のように書いています。
<志野と織部も美濃窯で焼かれた。16世紀末に現れた志野は、日本で最初に作られた白いやきものであった。中国白磁への永い憧れの末に、長石釉によって、ふわりと淡雪のような、日本の温かい白を生みだした。志野茶碗を手にとると、見た目の温かさの一方で、どっしりとした石のような冷たさがあり、その意外性も魅力である。釉下に鉄絵で文様を描くことも、大きな革新であった。(略) 志野に少し遅れて生まれたのが、鼠志野である。まず鉄釉をかけ、文様の部分を搔き落としてから、長石釉をかける。すると文様は白く、その余の部分は長石釉の白とあいまって、青味がかった美しい鼠色となる。織部は17世紀初めから作られ、わずか十年ほどの間に、時代を塗りかえる新機軸を打ち立てた。円形を基準とするそれまでの規格を打ち破り、扇面形、誰が袖形、千鳥形など多彩な形のうつわを、艶めく緑釉で飾った。千利休の高弟である武将茶人、古田織部の名に由来するが、織部本人が直接関わったかどうかは不明である。(p.15)>
また、本書p.5には「作り手がデザインを決定したのではなく、誰が使ったのか、誰に向けて作られたのかという享受者の文化が、やきもののデザインには大きな影響力をもっていた」という文章があります。本書p.26の「平安京以来の都には、志野・織部の注文主であった富豪たちが暮らし」ていた、という文章と合せると、志野・織部のパトロンは京の豪商たちであり、彼らの文化が志野・織部のデザインに大きな影響力をもっていた、と考えることができます。
Ron.