名古屋市美術館で「没後90年記念 岸田劉生展」(以下「本展」)が開催されています。先日、名古屋市美術館協力会主催のギャラリートークに参加しました。担当は井口智子学芸課長(以下「井口さん」)。参加者は93人。2階講堂で簡単な説明を受けた後、展示室に移動してギャラリートークが始まりました。
◆2階講堂でのトーク

集まった参加者の前に井口さんが登場すると、着ていたのは協力会の会員さんからプレゼントされた手編みのケープ。麗子像の肩掛けに似た配色の素敵な品でした。「参加者が多いので、どこにいるか良く分かるように着てきました。近いうちに名古屋市美術館でも毛糸の肩掛けとおかっぱ頭のかつらを用意して、『成りきり麗子』が撮影できるコーナーを設けます」というお知らせもありました。

また、井口さんが資料を入れていたのは、しりあがり寿が描いた「麗子ちゃんトートバッグ」。「主催者の御厚意でギャラリートーク終了までグッズ売り場が開いています。売り場では2種類の図録を販売しています。一つは《麗子微笑》を表紙にした図録。もう一つは《道路と土手と塀(切通之坂道)》を表紙にした東京会場・山口会場で販売していた図録です。違うのは表紙だけで中身は同じ。図録に収録された『岸田劉生活動記録(山田諭編)』は、数多くの資料を読み込んで編集した、価値の高いものです」というコメントがありました。(注:「岸田劉生活動記録」は劉生に密着取材して書いたような中身が濃いものでした。井口さんの「岸田劉生と名古屋 ― 劉生の《舞妓図》と杉本健吉」も図録に載っています。図録は税込2,500円。この外、毛糸の肩掛けは税込13,200円、トートバッグは税込1,100円です)
岸田劉生(以下「劉生」)については「17歳で絵を学び始めて、38歳で死亡。20年を駆け抜けた天才画家」と、紹介があり「本展は、山田諭・京都市美術館学芸課長が名古屋市美術館に勤務していた頃から企画していた展覧会である」ことも紹介されました。
◆第一章 「第二の誕生」まで 1907-1913
劉生について井口さんは「1891年に東京銀座で生まれ、1900年代には独学で水彩画を描き始める。1907年制作の水彩画を見ると、才能があったことが分かる。転機は1911年。彼は、当時発行された雑誌「白樺」が紹介したゴッホやマチスの作品に影響を受けた。作品を真似るだけでなく、興味を持った要素を取り入れて自分のものとして積み上げていった。物を見る目の鋭さが、彼の能力」と解説。この外、作品番号(以下「No」)14《自画像》については「自分を主観的に見た、ゴッホやマチス風の作品」、No17《築地居留地風景》・No18《築地居留地風景》については「表現主義的な画風」と、コメントがありました。
作品の数が多いので、水彩画、外光派の油絵、当時流行のポスト印象派風の作品と、岸田劉生の作風が目まぐるしく変化していく様子がよく分かりました。
◆第二章 「近代的傾向…離れ」から「クラシックの感化」まで 1913-1915
井口さんは「劉生は流行を追うのではなく、古典に逆行。友人の顔や自画像を数多く描いた。彼の描写は、だんだん細かくなっていくとともに写実的になっていく」と、解説。この外、No21《B.L.の肖像(バーナードリーチ像)》・No24《裸婦》を紹介。No40《黒き帽子の自画像》(注:1階エントランスの画像の右側の作品)については「帽子はお気に入りのもの。パレットを手にしており、画家としての自分を描いている。自分の道を見つけていった」と、コメントがあり、「美しさを見いだす能力が高かった」と劉生を評した、武者小路実篤の言葉も紹介。
また、第二章の最後のほうに展示されているNo52《高須光治君之肖像》については「デューラーやファン・エイクの影響を受けて、初期のものと比べると写実的になり、肌の状態を生々しく描いている」と、コメントがありました。

第二章には「これでもか」というほど、数多くの自画像が並んでいます。壮観というだけでなく、作風が変わっていく様子がよく分かります。次から次に自画像を見ていると、劉生の熱気が伝わってくるようでした。
◆第三章 「写実の神秘」を超えて 1915-1918
第三章の前半は主に風景画、後半は主に静物画です。風景画については「劉生が代々木に引っ越した頃は開発が進んでいる時代。彼は外に出て、自然に人間が手を入れている風景を写生。No56《代々木付近(代々木付近の赤土風景)》を見ると、重要文化財の《道路と土手と塀(切通之坂道)》に描かれた二本の黒い影が電柱だったのが分かる。No61《冬枯れの道路(原宿付近写生)》は名古屋展のみの出品。こってり描いているところと、ざっと描いているところを描き分けている」と、コメントがありました。
No65《古屋君の肖像(草持てる男の肖像)》については「着物の形、肌の様子など、写実性の高い作品」と、コメントがあり、静物画のNo69《林檎三個》については麗子が「父 劉生」のなかで「この絵は病と斗う父が、自分の一家三人を林檎に託して描いたときいている」と書いていることと「茶色の机は劉生のお気に入りだった」ことが紹介されました。更に、No70《初夏の小路》については「二科展で最高賞の二科賞を受賞し、賞金100円を受け取った」こと、No75《川幡正光氏之像》については「デューラーの絵を基にしているが、アルファベットの代わりに右に漢字を書いている」こと、No78《静物(手を描き入れし静物》は「二科展で落選。手が描かれており、悪趣味といわれた。現在、手は塗りつぶされている。塗りつぶしたのは劉生ではないが、塗りつぶした人物が誰かは分かっていない」こと、などが紹介されました。
第三章には、井口さんが紹介した以外にも数多くの静物画を展示しています。No73《静物(赤き林檎二個とビンと茶碗と湯呑)》やNo77《静物(白き花瓶と台皿と林檎四個)》などの作品を指して、ある会員が「ジョルジョ・モランディの静物画みたい」と感想を呟きました。モランディの作品は2011年に名古屋ボストン美術館で開催された「恋する静物」展で見ただけですが、「確かに、そんな感じがする」と、私も思います。
◆第四章 「東洋の美」への目覚め 1919-1921
第四章には、数多くの麗子像が展示されています。井口さんは「劉生は、麗子を通じて自分の描きたいものを追求した。それは、劉生と麗子の共同作業。彼は麗子だけでなく、近所に住むお松さんもモデルにした。お松さんは麗子より年上で、利発な田舎娘。麗子像の肩掛けは、元はお松さんのもの。劉生は、ほころびのある肩掛けを気に入って、麗子のために用意した肩掛けと取り換えた。お松さんも喜んでいた」と、コメント。この外、No90《麗子座像》(注:1階エントランスの画像の左側の作品)については「この時期から、劉生は水彩画を描くようになる。油絵はじっくり描くが、水彩画は素早く描くことが出来る」と、No111《麗子微笑》(注:名古屋展の図録の表紙)については「肩掛けの質感にリアリティーがある。程よい感じで微笑んでいる。どこか現実、どこか非現実。超現実の世界」と、No108《麗子洋装之図(青菓持テル)》については「水彩画で、バーナード・リーチとお別れするときに着ていた洋服を描いている」と、コメントがありました。《麗子微笑》については、更に「おかっぱ頭、着物、肩掛けなど現実にあるものを、現実を超えた美しさで描いている。敢えて、顔を横長にしたり、手を小さくしたり、アンバランスにして描いている」と、解説がありました。
1階展示室の出口付近のケース内に5歳の頃の麗子の写真が展示されていました。麗子像よりもかわいい顔をしています。そういえば、2019年9月29日(日)にNHK/Eテレで放映された日曜美術館「異端児駆け抜ける! 岸田劉生」では、《麗子微笑》について「丸い顔に鼻筋が通っているのは、仏像を思わせる。仏像のような微笑みは際どい。俗っぽくなるかどうかの瀬戸際」という画家の証言や「西洋の油絵に東洋の美を盛り込んだもの。異端児がたどり着いた極み」という学芸員の解説がありました。
◆第五章 「卑近美」と「写実の欠如」を巡って 1922-1926
井口さんは「1923年9月1日の関東大震災で、劉生の自宅が半壊。9月13日に名古屋の片野元彦が劉生を訪ねてきて、名古屋に移住することになる。劉生が名古屋に住んだのは半月ほど。その後、京都に引っ越したが、名古屋は劉生にゆかりがある土地」と話し、No113《二人麗子図》について「名古屋展のみの出品で、二人とも麗子という不思議な世界」と、No116《麗子微笑》・No117《麗子》については「グロテスク」と、No125《童女舞姿》については「名古屋展のみの出品」と、No135《少年肖像(村上巌氏十七歳)》については「能面のようで、日本画のようにのっぺりとした作品」と、コメントがありました。
第五章には、数多くの日本画を展示しています。井口さんから「劉生の日本画がこれほど集まる展覧会はない。No138《瓜之絵》は、日本画の冬瓜。京都時代の劉生は、あまり評価されていないが、力を蓄えていた時代」と、解説がありました。
第五章の日本画は、それまでの劉生と違い、肩の力が抜けたというか、ヘタウマというか、作風が大きく変わったことが分かります。
◆第六章 「新しい余の道」へ 1926-1929
井口さんから「孤立していた劉生のために、武者小路実篤が1927年に第1回大調和展を企画。劉生は《舞妓図》を出品(注:図録に、《舞妓図》について書いた井口さんの文章が載っています)。1929年には、南満州鉄道株式会社から招聘があり、再起をかけて満州に渡りますが、いい結果が出ず、帰国後、徳山で急逝します。No152《塘芽庵主人閑居之図》には、丸々と太った自分を描きこんでいます。太ったことも病気の原因かもしれません。彼は、癇癪もちでしたが、人間的な人でした。情の熱い人で、キリスト教を捨てたとしているが、人を超えた何かを信ずる人でした」という話があり、ギャラリートークは終わりました。
No160《満鉄総裁邸の庭》など、満州で制作した明るい色彩の作品を見ていると、徳山で急逝しなければ数多くの新たな作品が生まれていたように思え、残念でなりません。
◆最後に
本展を見終わって、監修した山田諭・京都市美術館学芸課長の意気込みを強く感じました。まさに「緻密な研究に裏付けられたすぐれた展示」という展覧会評(日経新聞2019.12.10文化欄)のとおりだと思います。見逃せない展覧会です。図録もお忘れなく。
Ron

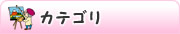
コメントはまだありません
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.